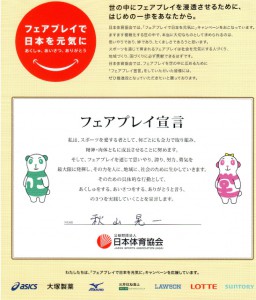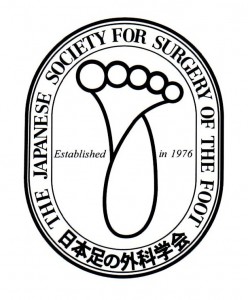三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会奈良県大会準決勝
2013年11月11日(月) 院長ブログ
|
昨日、天理親里球技場で第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会奈良県大会準決勝が行われ、グラウンドドクターとして参加致しました。 昨日の2試合では、特に目立った外傷もありませんでした。将来性豊かな選手たちが大きな怪我に見舞われることがなく、安堵致しました。 勝ち上がったのは天理高等学校と御所実業高校です。両チームともに実力はかなり高く、どちらが勝っても全国大会でも活躍できると思われます。 来週の決勝戦は激戦必至ですね!とても楽しみです。 |

日本体育協会公認スポーツドクター研修会
2013年11月07日(木) 院長ブログ
|
先日、日本体育協会公認スポーツドクター研修会が和歌山市で開催され出席しました。 今回のテーマは「ドーピング防止活動の最近の動向」、「日本におけるスポーツ外傷サーベイランスシステムの構築」、「スポーツ選手の脊椎障害と内視鏡手術」、「スポーツに関連した突然死とその予防」でした。 2020年東京オリンピック招致成功を受けて、日本のスポーツ界では様々な動きがあるようです。2020年に向けて、どんどん盛り上がっていくといいですね。 ドーピングに関してはまさにスポーツ界の負の側面でしょう。ドーピングはスポーツの価値を否定し、フェアプレイの精神に反し、競技者の健康を害し、反社会的行為であるなどということから厳格に禁じられています。ドーピング違反に対する制裁措置が現在2年間資格停止ですが、今後4年間に延長される可能性があるということです。今までは尿検査だけでしたが、これからは血液検査も施行されるようです。また今回の東京オリンピック招致成功には、ライバル国に比べてドーピングに関して日本がクリーンであるという評価が高かったという側面もあるようです。 スポーツ外傷サーベイランスでは、部活動中のスポーツ外傷の発生率は約10%で、1年間に10人に1人が受傷する割合だそうです。 中高生の部活動中の重症頭頸部外傷は種目ではラグビー、柔道、体操などの競技に多く、特に高校生ラガー、中2、高1の柔道選手に発生率が高いようです。 中高生の部活動中の膝前十字靱帯損傷は、女子が男子の3倍の発生率で起こるようです。種目別では男子では高校生ラガー、高校生柔道選手、女子では高校バスケットボール選手に多く発生し、特に高校女子バスケットボール選手では1年間で100人に1人の部員が膝前十字靱帯損傷を受傷しているそうです。中高生の部活動中の膝前十字靱帯損傷は増加してきており、年間3000件も起こってきているそうです。これには何らかの対策が必要ですね。 中高生の部活動中の足関節捻挫は、女子が男子の2倍の発生率で起こるようです。種目別ではバスケットボール、バレーボール、サッカー、ラグビーなどに多く発生する様です。男子では中2、高2のバスケットボール、バレーボール選手、女子では中学バスケットボール選手に多いようで、1年間に20人に1人の部員が足関節捻挫を受傷する様です。これにも何らかの対策が必要と思われます。 日本におけるスポーツ外傷サーベイランスシステムの構築として、全国的なスポーツ外傷統計は児童、生徒以外は十分とは言えず、特に大学生、社会人での取り組みが必要であるとのことです。スポーツ外傷・障害の予防プログラムの開発や検証については、各競技で進めていき、長期的に継続してみていく必要があるということでした。 スポーツ選手の腰椎椎間板ヘルニアに対しては、内視鏡手術と術後のアスレチックリハビリテーションを施行することにより、94%が2ヶ月以内にスポーツ復帰が可能であったそうです。 スポーツ中の突然死の頻度は20万人に1人の割合で、一見健康な若い運動選手が運動中に心室頻拍または心室細動を突然発症し、急死してしまいます。男性は9倍多く罹患し、アメリカではバスケットボール選手、フットボール選手、ヨーロッパではサッカー選手、日本では剣道選手のリスクが高いそうです。 肋骨、胸骨、心臓自体の構造的異常がなくても、前胸部の打撲で心室細動が誘発されて起こる心臓振盪は、野球、ホッケー、ラクロス、空手などの打撃系のスポーツでよく起こります。2007年に岸和田市で高校野球の試合中に胸部に打球を受けた選手がその場で倒れ、心肺停止状態になった事例がありました。観戦していた同市消防本部の救急救命士がAEDを使うなどしたため、一命を取り留めたそうです。 心臓突然死を防ぐためには心電図なども含めた健診を受けることとともに、失神の既往などの問診、家族内(3親等以内)突然死の既往などの家族歴が重要です。 研修の時に日本体育協会の方に配って戴いたのですが、日本体育協会では「フェアプレイで日本を元気に」キャンペーンを行っているそうです。日本体育協会の考えるフェアプレイには行動としてのフェアプレイとフェアプレイ精神(フェアな心、魂)の2つの意味があるそうです。具体的な行動としては「あくしゅ、あいさつ、ありがとう」の実践を掲げています。2020年東京オリンピックに向けて、フェアプレイの精神と気運が日本で拡がっていくといいですね! |

第38回日本足の外科学会
2013年11月04日(月) 院長ブログ
|
10月31日、11月1日に仙台市の仙台国際センターで第38回日本足の外科学会が開催され、1日目に参加致しました。 4つの講演会場とポスターセッションが同時に行われ、大変盛況な学会でした。 基調講演は日本足の外科学会理事長木下光雄先生が「日本足の外科学会の現状と課題」を講演されました。本学会の歴史から、世界における本学会の立ち位置、進むべき方向などを示して下さいました。また哲学者中村雄二郎著書「臨床の知とは何か」や野口裕二著書の「ナラティブ・アプローチ」を紹介して下さり、木下光雄先生の幅広い見識の深さが伺えました。 「アスリートのスポーツ傷害に対するLIPUSの効果」を帝京大学整形外科松下隆先生が講演されました。LIPUSは低出力超音波パルス治療法のことで、体表に置いたプローブから照射されるパルス波が骨折部を機械的に刺激することにより、骨癒合期間を短縮させる非侵襲的な治療法です。骨折の骨癒合期間は38%短縮されるというデータがあるそうです。現在、難治性骨折や新鮮骨折に対する観血的手術症例などに保険適応がありますが、疲労骨折や偽関節に対しても効果が見込めるそうです。またLIPUS照射により線維芽細胞が誘導されることから、軟部組織損傷に対する効果も期待されています。保存治療に抵抗した短距離走者のアキレス腱症にLIPUSを応用したところ、治療開始後3ヶ月で競技復帰した症例を紹介して頂きました。 今学会では創傷治癒のセッションの座長を務めさせて頂きました。皮膚欠損創に対して陰圧閉鎖療法や遊離筋皮弁を用いた治療経験の演題でしたが、いずれも困難な症例をうまく治癒に導いている報告でした。 |

市民公開講座が開催されました。
2013年10月20日(日) 院長ブログ
|
昨日、ヒルホテルサンピア伊賀にて市民公開講座が開催されました。 今年のテーマは「ロコモティブシンドロームと関節の変形」です。 悪天候にもかかわらず大変大勢の方が来場され、熱気あふれる雰囲気でした。 演題1は「栄養とロコモティブシンドローム」で講師は名張市立病院管理栄養士松本優子先生でした。カルシウム、タンパク質など色々な栄養をバランスよく摂ることが必要とは言われますが、具体的にどの様なすればよいのかわかりにくいですね。実際のレシピの工夫を紹介して頂き、ちょっとした工夫で栄養素のバランスが大変良くなることがわかり、とても参考になりました。中年期にメタボ対策でカロリーを控えることが強調されるので、高齢期になっても必要以上にカロリーを控えてしまうことがロコモの危険性を高めるということは成る程と思いました。年代によって必要とされる栄養も変わってくるということですね。 演題2は「変形性膝関節症」で講師はおおすみ整形外科院長大角秀彦先生でした。変形性膝関節症の病態と治療、日常生活での工夫など大変わかりやすく解説して戴き、聴衆の皆様もとても理解しやすかったのではないでしょうか。また大角院長の立派な獲物の数々も披露して頂きました。おおすみ整形に行けば、巨大な魚拓もご覧頂けるということでした。 演題3は「膝への負担を減らす運動療法」で講師はいまむら整形外科理学療法士森統子先生でした。膝を支える一番大事な筋肉は太ももの前の大腿四頭筋という膝を伸ばす筋肉ですが、この大腿四頭筋の中でも内側広筋、大腿直筋、外側広筋のそれぞれを別々に鍛える運動療法を紹介して頂きました。これはわかりやすいですね!皆さん、とても参考になったことと思います。 ご来場戴きまして、誠にありがとうございました。 |

疼痛に関する講演会
2013年10月13日(日) 院長ブログ
|
先日、津市で疼痛に関する講演会があり出席しました。 講演1は「運動器疼痛の基礎と臨床~関節疾患を中心に~」で講師は藤田保健衛生大学病院整形外科准教授森田充浩先生でした。森田充浩先生は関節リウマチ、股関節外科などを専門にしておられ、アメリカなどへの留学歴も豊富な経験豊かな先生です。森田充浩先生によりますと、日本では疼痛を愁訴として持っておられる方の割合は男性20%、女性25%、全体で22.9%だそうで、これはとても多い割合ですね。しかしながら現在の薬の治療に満足しておられる方の割合は27.2%であると、整形外科にとって厳しいデータも紹介して頂きました。日本では疼痛に対しては、まずNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が使われることが多いですが、アメリカでは第一選択がアセトアミノフェンだそうです。森田充浩先生は関節疾患で治療に大変難渋するような数々の困難な症例を紹介して下さいましたが、創意工夫を持って粘り強く治療しておられることに感銘を受けました。 講演2は「腰痛治療の最前線」で講師は帝京大学ちば総合医療センター教授豊根知明先生でした。脊椎炎に対して創外固定を用いて見事に治癒に導いた症例、椎間板性腰痛に対する前方固定術、成人の脊椎変形(腰曲がり)に対する椎体骨切り術など、どれも見事な治療の数々でした。椎間板性腰痛ではMRI検査画像所見による変性腰椎の骨性終板の輝度変化(Modic change)が参考になるそうです。脊椎変形に対する椎体骨切り術は、かなり難易度の高い手術治療と思われますが、仙骨の傾き、骨盤の後傾などのパラメーターから骨切りの角度を決定するそうです。脊椎後弯などの脊椎変形が進行してしまい、円錐の空間からはみ出てしまうと姿勢の保持が困難になるという説明は成る程と思いました。 さらに腰痛に対する薬物療法に関しても詳細に説明して下さいましたが、最先端の手術治療から薬物療法まで網羅しておられる豊根知明先生に感心しきりでした。 豊根知明先生の親友という落語家の桂三輝(かつらサンシャイン)さんについても紹介して頂きました。桂三輝さんはカナダ出身で桂三枝さん(現・六代桂文枝)の弟子で、現在「あなたの街に住みますプロジェクト」で三重県伊勢市に住んでいるそうです。豊根知明先生はなんと桂三輝さんと焼き鳥屋で偶然知り合いになったそうです。豊根知明先生の人脈の広さにも感心致しました。 |