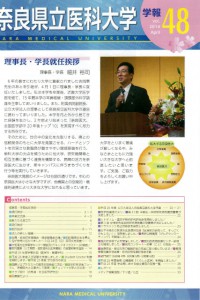三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


倭の会
2014年07月30日(水) 院長ブログ
|
先日、奈良医大昭和63年卒業(倭の会)・昭和57年入学同窓会が開催され出席しました。奈良医大昭和63年卒業生の同窓会のことが「倭の会」と名付けられています。本会は4年ぶりの開催です。私は診療の後片付けに手間取り、随分遅刻しての参加となりました。 同級生の中で最も年が若い人は、現役で昭和57年に入学した昭和39年3月生まれの人だと思いますが、その方でも既に50歳になっています。つまり本会に参加した人は全員50歳以上になります。同級生で現役入学の方はおそらく2~3割くらいでしょうか?私も浪人しましたが、浪人して入学してくる人がほとんどで、中には社会人を経て奈良医大に入り直してくる方も結構おられまして、同級生でも10歳以上年長の方も数名はおられました。大学1年生の時には私は19歳でしたから同級生でも30歳以上の方のことはとても大人(オッサン)に見え、同級生とは思えませんでした。それから30年以上経って、全員が50歳以上の「余裕でオッサン」になってしまいますと10歳の年の差は、ほとんど誤差範囲になってしまっていました。 4年前と違い開業している方が増えて、病院勤務医の方が少数派になったかもしれません。私も4年前の同窓会の開催された少し後で病院勤務医を辞し開業しました。開業医の方も皆さんそれぞれの地域で頑張っておられるようですが、病院勤務医の方もそれぞれの専門性を高めて、指導者としての立場で活躍しておられるようです。同級生の中でも大学教授になって活躍している方も数名おられます。特別な才能のある方には、日本の医療の最先端を牽引していって欲しいですね。 会で同級生のE君に会ったときに言われました。大学1年生の時に部活動を続けるかどうか悩んでいたE君は当時私にこのことを相談してくれたそうです。そこで私がなんとアドバイスしたのかをE君に尋ねますと、当時私はE君に「好きに、せいや!」と言い放ったそうです。…ウーン、これは身も蓋もない返答ですね。さすがに30年の時を経て、私はこう言ったことは全く憶えていません。E君にこのことを相談はされたような気はします。ようやく今になってですが…。E君、スマン!これは時効ということで…。 しかしながら人の記憶には時効はありません。E君はこのことを一生、忘れないことでしょう。 30年前にタイムスリップしたような気がして、本当に楽しい時を過ごさせていただきました。 幹事のN君、M君ありがとう!ご苦労様でした。 |

「OAの新しい画像診断法と臨床への応用」
2014年07月27日(日) 院長ブログ
|
第27回臨床整形外科学会で初日のモーニングセミナー1が行われ、講演は「OAの新しい画像診断法と臨床への応用」で講師は千葉大学大学院医学研究院総合医科学講座東千葉メディカルセンターの渡辺淳也先生でした。 OAとはOsteoarthritis(変形性関節症)のことで、様々な原因により関節の痛みや腫れを生じ、それが続くと関節の変形をきたす病気です。整形外科のあつかう疾患の中で最も多い疾患の一つと言えるでしょう。OAは関節への繰り返す微小外力や加齢に伴い生じた退行変性を基盤として発生しますが、OAの初期に起こる変化は関節軟骨の変性です。渡辺淳也先生によりますと、関節軟骨は水分が70~80%、コラーゲンが15~20%、プロテオグリカンが2~5%で、血管に乏しく細胞密度が低いために、プロテオグリカンの減少やコラーゲン配列の不整化などが起こりやすいそうです。関節軟骨機能低下は軟骨自体の摩耗に加え周囲の骨増殖性変化を生じ、最終的に不可逆的な関節変形へと進行します。渡辺淳也先生によりますと、進行したOAに対しては外科的治療以外に有効な手段がないため、なるべく早期にOAの診断をし、進行予防のための有効な対策を取ることが大切であるということです。 MRI(磁気共鳴撮像)は、単純レントゲン写真では評価困難な関節軟骨など軟部病変の検知が可能であり、渡辺淳也先生は近年の新しいMRI検査の進歩で、形態学的評価に有用な3D isotropic MRIと質的評価に有用なT2マッピング、T1ρマッピングを紹介されました。渡辺淳也先生はこれらのMRI撮像法がレントゲン撮影や従来のMRI撮像法では検知できない早期の軟骨変性を捉えることが可能であり、また軟骨変性度を定量的に評価可能であることを示されました。 現在のところOAに対する疾患修飾性作用薬として臨床応用されているものはありません。渡辺淳也先生によりますと、ヒアルロン酸製剤、COX-2選択的阻害薬、骨粗鬆症治療薬の一部などが基礎的実験などにおいて軟骨保護作用を示すことからOAに対する疾患修飾性作用薬としての候補として挙げられるそうです。ヒアルロン酸を投与することにより粘弾性が上昇し、これにより人工膝関節置換術施行までの期間を延長することができたり、軟骨体積減少抑制を認めるそうです。OAにおける軟骨下骨変化と軟骨変性との関連性が研究されており、軟骨下骨脆弱化と軟骨変性が関連しているということです。このことにより骨粗鬆症の一部は、投与により関節裂隙狭小化が改善されたという報告もあるそうです。今まで骨粗鬆症とOAは原因も治療薬も別ですよ、と私も常々患者様に説明いたしておりましたが、今後は少し話が変わってくるのかもしれません。 渡辺淳也先生は基礎研究と臨床研究をリンクさせて大変興味ある研究をしておられ、とても感心致しました。 |

第27回日本臨床整形外科学会
2014年07月21日(月) 院長ブログ
|
7月20日、21日と仙台におきまして、第27回日本臨床整形外科学会が開催されました。初日の7月20日に、本学会に当院の理学療法士3人と共に出席しました。19日の深夜に私は仙台に到着しましたが、雨の影響か、仙台は思いの外涼しくてビックリしました。また帰りの新幹線では、倒木の影響で東北新幹線が、大雨雷雨の影響で東海道新幹線が一時運転を見合わせたために随分遅れてしまい、名古屋ではぎりぎり最終の近鉄電車に間に合い何とか名張に帰ってくることができました。 本学会では当院からは理学療法士小野正博が演題「橈骨遠位端骨折変形治癒例における理学療法経験」を発表し、こちらも無事に終わりました。 この学会で得た知識を、日々の臨床に役立てたいと思っております。 |

「野球肘のリハビリテーション」
2014年07月18日(金) 院長ブログ
|
第30回三重上肢外科研究会の特別講演Ⅱは行岡病院リハビリテーション部理学療法科長山野仁志先生でした。 山野仁志先生は自身が野球選手として怪我に苦しんで断念せざるを得なかった経験をもとに、野球少年に自分と同じ思いをさせたくないという気持ちで現在の職に就き治療にあたっているそうです。また行岡病院整形外科副院長正富隆先生との出会いが、本当に自分の方向性を強固なものとし経験を高めることができたと感謝しておられました。 山野仁志先生は野球肘のリハビリテーションを次のように進めるそうです。 ①肘周囲筋柔軟性改善、②肩関節後方の伸張性改善(肩屈曲90度での内旋可動域改善)、③外旋筋力の強化、④投球動作の改善 肘周囲筋柔軟性改善では前腕屈筋、前腕伸筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋の順にストレッチの方法を紹介されました。 肩関節後方の伸張性改善では腹臥位で肩甲上腕関節の内旋可動域改善のための肩関節後方ストレッチングを紹介されました。これは野球肘の原因となる肘外反ストレス、伸展ストレスを回避するために重要であるようです。 外旋筋力の強化として側臥位と腹臥位で行う肩関節外旋筋力トレーニングを紹介されました。次に腹臥位で行う肩甲帯筋力トレーニングと、片手支持の腕立て伏せ位で行う肩甲帯筋力トレーニングを紹介されました。投球動作でボールリリース時に肩内旋動作により肩外旋筋にかかる強力な遠心性筋力(ブレーキング作用)が重要で、前鋸筋、僧帽筋下部の筋力が重要であるようです。 投球動作の改善としてまず肘痛が出る動作と出ない動作を自覚し、正しい投球動作に対する誤解を改め、正しい投球動作のイメージを持つことから始め、段階的にスローイング動作を会得していく方法を紹介されました。ポジションごとに必要な投球動作を改善していくことが重要であるようです。 講演では実際に野球経験者をモデルにして投球動作の改善指導が行われました。一歩ずつ段階を踏みながら、選手がわかりにくいときには選手の理解を助ける引き出しもたくさんお持ちのようです。野球のことは全くわからない私でも成る程!と思うところの多いわかりやすい指導でした。 山野仁志先生の野球選手に対する愛情が伺えました。
|

第30回三重上肢外科研究会
2014年07月14日(月) 院長ブログ
|
先日、第30回三重上肢外科研究会が開催され出席しました。 特別講演Ⅰは「野球肘の診断と治療・予防」で講師は行岡病院整形外科副院長正富隆先生でした。 正富隆先生は大阪大学整形外科、大阪厚生年金病院などで勤務してこられ、現在行岡病院手の外科センター長を務められる手の外科、上肢外科のスペシャリストです。正富隆先生は阪神タイガースのチームドクターも勤めておられ、阪神タイガース選手の治療にもあたっておられます。 サッカー人気に少し押され気味とはいえ、野球はまだまだ日本では最も人気のあるスポーツであり注目も集めます。最近のメジャーリーグでの様々な日本選手の活躍も誇らしい限りですね。しかしながら野球の場合は肩や肘に負担がかかりすぎてしまい、傷害を起こしてしまったり競技を断念せざるを得ないケースもあります。今回、野球選手の治療経験豊富な正富隆先生の講演は大変勉強になり、今後の臨床に活かしていきたいと思いました。 野球肘といいますと、投げ過ぎ(オーバーユース)と捉えがちですが、正富隆先生によりますと普段の投球でストレス過剰になっている、すなわちフォームの悪い投げ方であったりコンディション低下などが原因であるということです。確かに同じように投げていても傷害を起こす選手と起こさない選手がいます。また傷害を起こした選手が靭帯再建術などの手術治療を受けた場合でも、他の部位(膝関節など)の治療に比べて長期間要することが多いのは、フォームやコンディション低下などの問題を克服できずに同じ部位を痛めてしまうことが多いからだそうです。 野球肘には内側型、外側型、後方型などありますが、内側型と外側型は肘外反力、後方型は伸展力がかかることにより生じます。肘関節にとって投球動作による外反ストレスは非生理的運動になります。 診察においては圧痛部位を丹念に観察する必要があり、内側型では内上顆障害、内側側副靱帯損傷、回内筋付着部炎などの鑑別が重要です。正富隆先生によりますと離断性骨軟骨炎が単独で生じることはむしろ少なく、靱帯損傷を伴っている場合が多いそうです。 徒手検査で外反ストレステストではMoving valgus stress test、Milking testなどが有用ですが、疼痛の誘発と共に脱臼不安感の出現がポイントであるそうです。 肘内側側副靭帯損傷では1974年にメジャーリーガーのトミー・ジョン投手が、フランク・ジョーブ医師による肘内側側副靭帯再建術を受けて見事に復帰してから既に40年が経過しましたが、これまでに100名以上のメジャーリーガーがこの手術を受けているそうです。日本球界でも1983年に村田兆治投手がフランク・ジョーブ医師の手術を受けて復活を果たし、今までに30人以上の日本人選手もアメリカで手術を受けているそうです。正富隆先生は肘内側側副靭帯のIsometric fiberに注目し肘内側側副靭帯再建術における内側上顆の骨孔の位置に工夫を凝らし、良好な治療成績をあげておられるようです。しかしながら正富隆先生は手術治療に至るまでの保存治療の重要性、手術治療の適応を十分に検討することを強調しておられました。 後方型は伸展力による肘の傷害でインピンジメント、肘頭疲労骨折、骨端線閉鎖不全などがあり、肩関節後方タイトネスと肩甲骨の動きが影響するそうです。正富隆先生は肩関節後方ストレッチの重要性を強調しておられました。 正富隆先生は野球肘に対して、休めることを指示しておくだけ、あるいは手術するだけでは不十分であると指摘されます。コンディションやフォームを改善するリハビリテーションを行うことにより、手術回避、早期復帰、再発防止に繋げることが重要です。正富隆先生によりますと野球肘を診るときには肘だけでなく肩、さらに体幹、下半身にも注目することが重要です。 実は、正富隆先生は大阪府立天王寺高校ラグビー部出身で私の2年先輩になります。私が高校1年生の時には、高校日本代表選手であった一井主将とともに正富隆先輩はFWリーダーとしてチームの中心選手として活躍しておられました。偉大な先輩の講演を聴くことができまして、大変感激いたしました。 |