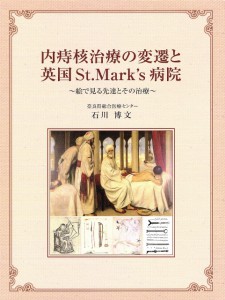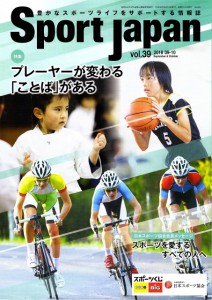三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


「内痔核治療の変遷と英国St. Mark’s 病院」
2018年10月13日(土) 院長ブログ
|
奈良県総合医療センター外科、中央手術部部長石川博文先生著の「内痔核治療の変遷と英国St. Mark’s 病院」を読みました。 本書に「推薦のことば」を送っておられる、がん研有明病院名誉院長武藤徹一郎先生の言葉によりますと、St. Mark’s Hospitalは多くのColoproctologistにとって憧れと敬愛の象徴と言ってもよいだろう、ということでした。私は不勉強にもColoproctologistという言葉を知りませんでしたが、Coloproctolyは大腸肛門病学で、消化器・総合外科の中でも大腸肛門疾患の外科治療を専門にされる先生方のようです。 世界初の肛門専門病院という英国St. Mark’s 病院は1835年に開設されたそうで、内痔核の外科治療で痔疾患のメッカと呼ばれていたそうです。石川博文先生は1999年から2年間、英国St. Mark’s 病院に留学されたということで、本書は近畿肛門疾患懇談会の会誌”臨床肛門病学”に掲載された原稿をまとめたものであるということです。また、この執筆がきっかけとなり石川博文先生はベルリン医学協会から招待され、ドイツから伝わったLangengeck法とBraatz法の意義や日本とドイツの絆について、ドイツベルリンでご講演されたそうです。 本書を読ませていただきますと、写真が豊富で外科学の歴史教科書の様な趣で、石川博文先生のColoproctolyに対する熱意が伝わってくるようで、さすが実直な石川博文先生が心を込めて丹精に作り上げた本であると思いました。提示された図は合計97枚におよぶそうです。さらに207編という膨大な文献を集めて、全てに目を通されたとのこと、最も古い文献は1664年のものもあるということでした。何事も妥協を許さず道を究められる、石川博文先生らしいことだと思いました。 ちなみに石川博文先生は学生時代に奈良医大ラグビー部で私の2年先輩であり、ポジションは左プロップをしておられました。当時、医学生とは思えない屈強のスクラマーであったことが印象的です。 石川博文先生が外科医を志すきっかけになったという「過去を記憶しえない人々はその過去を再び経験することになる」というGeorge Santayanaの言葉は、胸に刻むべき言葉であると思いました。 |

Sport Japan
2018年10月04日(木) 院長ブログ
|
Sport Japan vol.39の特集は“プレーヤーが変わる「ことば」がある”です。 言霊専門家の七沢賢治氏によりますと、他言語に比べ日本語はよりパワーを持つということです。言霊とはエネルギーを結合することであるそうです。フィギュアスケート宮原知子選手のコーチである濱田美栄氏が、平昌で宮原知子選手を自己ベスト更新へと導いた一言を紹介しています。 日本ペップトーク普及協会専務理事浦上大輔氏がペップトークの4ステップを紹介しています。ペップトークとはスポーツの試合前に指導者がプレーヤーに対して行う激励のショートスピーチであるそうです。ペップとは英語で元気、活気という意味であるそうです。これは色々な場面で応用できそうですね。 ペップトークを組み立てるには受容→承認→行動→激励の4つのステップが効果的であるということでした。相手にもっとよくなってほしいという気持ちから、ついネガティブな言葉を投げかけて相手のやる気を削いだり、説教や命令になってしまっているペップトークと反対の言葉を“プッペトーク”と呼んでいるそうです。 自分も、ついプッペトークをしてしまっていないか、と思わず内省させられる記事でした。 |

敬老の日
2018年09月17日(月) 院長ブログ
|
新聞によりますと、「敬老の日」を前に総務省が65歳以上の高齢者の推計人口(15日時点)を3557万人と公表し、総人口を占める割合は28.1%と過去最高を更新したそうです。70歳以上は2618万人で全体の20.7%を占め、「団塊の世代」が70歳を迎え始めたことが影響しているそうです。高齢化進行の速さには驚くばかりですね! 高齢者割合は世界でもダントツの一位ということで、世界でも類を見ない異次元の状況になってきているようです。医療や福祉の世界でも、他分野と同様に色々な面での変革は避けられない状況なのでしょうね。 |

「“長寿菌”がいのちを守る!~大切な腸内環境コントロール~」
2018年09月06日(木) 院長ブログ
|
本日、アドバンスコープADSホール(名張市青少年センター)におきまして名賀医師会主催の救急医療週間の講演会が開催されました。特別講演は「“長寿菌”がいのちを守る!~大切な腸内環境コントロール~」で講師は国立研究開発法人理化学研究所辨野義己先生でした。 便の(べんの)研究をしておられる辨野(べんの)義己先生は、もう45年間も腸内細菌の研究をしておられるそうです。辨野義己先生によりますと加齢により腸の中の老廃物を出す力(腸管運動)が低下し、腸内に有害な腐敗物質がたまりやすくなるそうです。また腸内細菌は10%が悪玉菌、20%が善玉菌、残りの80%が日和見菌だそうですが、加齢によりこのバランスが崩れ、善玉菌が急激に減少し悪玉菌が増加してくるそうです。以上の「腸年齢の老化」により、腸内腐敗によって作られた有害物質が腸管から吸収され、老化がさらに加速するという悪循環が生まれるそうです。辨野義己先生によりますと肥満の人、ストレス過多の人で特に腸の老化が進行しているという調査結果であったそうです。”健康長寿者”に共通する生活習慣は野菜をたくさん食べている、身体をよく動かしているなどであるそうです。辨野義己先生によりますと健康長寿者の腸に多い腸内細菌は「大便桿菌」と「大便球菌」で、どちらも「酪酸」という物質を作る「酪酸産生菌(酪酸菌)」であるということです。もう一つ健康長寿者に多いのは善玉菌の代表である「ビフィズス菌」だそうです。辨野義己先生はこれらの腸内細菌のグループを総称して「長寿菌」と呼ぶようにしたということでした。腸内環境の善し悪しは、毎日自分で目と鼻で自分の便を確認することにより測ることができるので、「便所は便器のある所ではなく、身体からのお便りを受け取るところ、すなわちお便り所が便所です。」と辨野義己先生はおっしゃられました。辨野義己先生によりますと食生活でいいウンチを作り、運動で筋力をつけてしっかり出すことが肝心で、トイレでのチェックで「臭いがきつくなく、黄色から黄褐色がかったウンチを、毎日バナナ3本分ほど出す」ことが良い腸内環境を産み出す極意であるということでした。約500名の参加された皆様は辨野義己先生のお話を大変興味を持って聞いておられた様子でした。 特別講演の後には名張消防署職員(救急救命士)、女性消防団員によるAED、心肺蘇生法の説明、実演「あなたの勇気が命を救う」が行われ、救命処置をわかりやすく解説して下さいました。日本では年間約10万人の突然死があり、このうち約6万人が心臓突然死であるそうです。1日に160人もの人が心臓突然死している計算になるそうです。AEDを使用することにより心肺停止状態の方を救命できる可能性が上昇するため、AEDを必要なときには躊躇わずに使用することが重要であるということでした。若くして心臓突然死で亡くなられた方々の生前の写真が写った、心臓突然死啓発映像「あなたにしか救えない大切な命~君の瞳とともに~」を見せていただきました。胸に迫る映像で、改めてAEDの重要性を強く感じました。 本日は、本当に大勢の方が講演会にお越し下さいました。誠にありがとうございました。 |