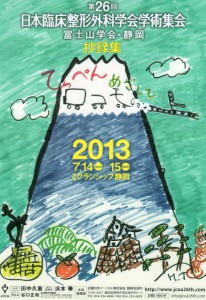三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


iPSで膝関節再生
2013年08月18日(日) 院長ブログ
|
8月16日産経新聞にこの様な記事が掲載されました。 実現すれば画期的な治療方法ですね!今後の進展を見守りたいです。 15年後の実用化を目指しているそうです。
|

ひざ痛 1800万人
2013年08月15日(木) 院長ブログ
|
8月13日の朝日新聞夕刊にこの様な記事が掲載されました。 膝の痛みに悩む中高年は1800万に上ると推計され、変形性膝関節症の方は要介護になるリスクが5.7倍高くなるそうです。65歳以上の高齢者に限ると35%が膝の痛みに悩んでいることになるそうです。 運動機能低下が要介護になるリスクを高めることが明らかになり、膝に負担のかからない運動を続けることがひざ痛を予防し介護予防にもつながるようです。 日本整形外科学会などで作る「ロコモチャレンジ推進協議会」は、膝痛を予防する運動療法を紹介しています。 それにしても地方に住む人が都会に住む人に比べ、要介護になるリスクが1.6倍高いことは不思議ですね。地方にすむ人の方が公共機関が不便で、歩く機会が少ないからということですが…。これはどうなんでしょうか? |

ロコモ認知度26.6%
2013年08月02日(金) 院長ブログ
|
2012年3月に国民のロコモ認知度は17.3%であったのが、2013年3月には26.6%に増加していたそうです。 ロコモティブシンドローム(ロコモ、運動器症候群)は運動器の障害のために移動能力の低下をきたして、要介護になっていたり、要介護になる危険の高い状態をいいます。筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、歩行や日常生活に何らかの障害をきたしている状態をいいます。 日本整形外科学会ではロコモの普及活動に取り組んでおり、10年後には国民のロコモ認知度80%を目指しています。 超高齢社会を迎える日本では、寝たきりにつながるロコモ対策が必須です。 われわれも啓蒙活動にしっかりと取り組んでいきたいと思います。 |

「スポーツにおけるドーピング~全てのドクターに知っておいて欲しいこと~」
2013年07月21日(日) 院長ブログ
|
先日、奈良県医師会スポーツ医学部会主催の講演会があり出席しました。演題は「スポーツにおけるドーピング~全てのドクターに知っておいて欲しいこと~」で講師は今回も奈良教育大学保健体育講座学校保健・スポーツ医学研究室教授笠次良爾先生でした。 ドーピング検査といいますとオリンピックなどでの報道を思い出しますが、国内でも国体や全国大会などで年間約5000件のドーピング検査が施行されているそうです。国内の場合は競技力向上目的の薬物使用ではなく、治療のために服用した薬が禁止薬物であったという「うっかりドーピング」がほとんどであるそうです。 ドーピングとは、競技力を高めるために薬物などをしようしたり、それらの使用を隠したりする行為です。どういう行為がドーピングに当てはまるかは世界ドーピング防止規程に定められており、意図的ではなく不注意であっても制裁の対象になります。 日本アンチ・ドーピング機構(JADA)によりますとドーピングが禁止されている理由として、フェアプレイの精神に反する、健康を害する、反社会的行為などもありますが、スポーツの価値を損なうという面を強調しています。しかしながら、かつての旧東ドイツなどでは元オリンピック選手のドーピング後の後遺症による健康被害は深刻であるそうで、健康を害するという面が大変重要であることは間違いありません。 世界ドーピング防止機構(WADA)が策定した禁止物質及び禁止方法は禁止表国際基準(禁止表)として、毎年更新されます。こういった情報も踏まえつつ、国体や全国大会などに出場するくらいの選手はかかりつけ医師に自分がアスリートであり禁止物質が入っていない薬の処方をお願いする必要があります。最新のアンチ・ドーピングに関する知識を持ち、薬の正しい使い方の相談ができる薬剤師であるスポーツファーマシストに相談するのも良いかもしれません。薬局やドラッグ・ストアで手軽に手に入る風邪薬や花粉症の薬にも、禁止物質が含まれているものがあります。 栄養補助食品(サプリメント)は薬ではなく食品に分類されるために、製品に成分の全てが表示されません。表示されていないものの中に禁止物質が含まれている場合もあり、特に海外製のサプリメントには禁止物質が入っている製品が多いのでより注意を要します。 漢方薬のなかには、主成分として禁止物質を含むものがあり、また全ての成分が明らかになっていない漢方薬もありますので注意を要します。 病気やケガの治療で禁止物質を使わざるを得ないときには、TUE申請を行って承認を得る必要があります。 ドーピング検査の実際も紹介して頂きました。一部の違反選手による隠蔽工作もどんどん巧妙に進んで、摘発する機構側とのいたちごっこですね。世界一を競うトップアスリートが不正行為の隠蔽工作に奔走するのは情けない限りです。まさに栄光の頂点から汚辱への転落ですね。 確かにこれはスポーツの価値を損なうものだと思いました。 |

第26回日本臨床整形外科学会学術集会
2013年07月15日(月) 院長ブログ
|
昨日、今日と静岡で第26回日本臨床整形外科学会学術集会が開催され出席しました。 本学会への参加は、私は初めてでした。 本学会は整形外科開業医が主体ではありますが、整形外科勤務医、そして理学療法士などのコメディカルも多数参加する、大変活気のある学会でした。会場も第9会場までありとても規模の大きな学会で、どの演題を聴こうかと迷ってしまうほどでした。 大変勉強になり、その内容はまた報告したいと思っております。 |