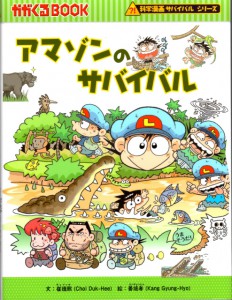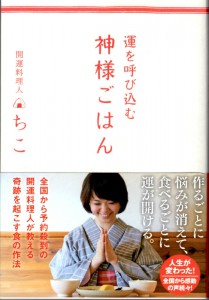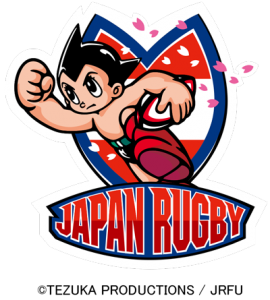三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


「認知症の鑑別診断」
2015年06月10日(水) 院長ブログ
|
先日、名賀医師会臨床懇話会が開催されました。特別講演は「認知症の鑑別診断」で講師は三重県立こころの医療センター院長森川将行先生でした。 厚労省のデータによりますと、2012年時点で認知症の方は約462万人おられ、2015年には700万人に達するという推計値を報告しています。つまり65歳以上の高齢者の5人に1人にあたる計算になるそうです。もの忘れは65歳以上の75%には認めるそうですが、もの忘れのパターンとしてあまり気にしなくてよい物忘れは部分的であり何かのきっかけがあると思い出すことができる、うっかり物忘れなどですが、認知症による物忘れになると日常生活上の出来事をまるでなかったことのように忘れてしまう、抜け落ちるように忘れてしまうことが特徴的であるそうです。記憶障害だけでは軽度認知障害ですが、失語、失行、失認、実行機能障害のどれか一つ以上が合併すれば認知症と診断されます。認知症における生活機能の障害となる中核症状は認知機能障害といい記憶障害、判断力低下、見当識障害、言語障害(失語)、失行、失認などですが、周辺症状としてせん妄、抑うつ、興奮、徘徊、睡眠障害、妄想などがあり、これら周辺症状として何らかのサインを出している可能性があり、こうした症状が引き金となり高齢者虐待に至ることもあるそうです。 森川将行先生によりますと認知症を引き起こす原因を考えるときに、全身性疾患と内服薬の影響を除外しつつ脳内の病因について検索を行うことが重要であるということです。内科的病因としては中毒、代謝性認知症など、薬剤の副作用としてさまざまな薬が原因となるそうですが、薬を追加しても減らしてもこういう減少が起こりうるということでした。 認知症の種類と割合ではアルツハイマー型が約50%、レビー小体型が約20%、脳血管性が約15%、その他が約15%だそうです。このうちレビー小体型認知症を疑うポイントとして、はっきりしている時とボーッとしている時があること(認知機能の変動)、実際にそこにない物が見えたり、いない人が見えることがあること(幻視)、体を動かしにくい、手足がふるえる、歩きづらいといった症状があること(パーキンソンにズム)、睡眠時に大きな声の寝言や異常な行動があること(レム睡眠行動障害)などがあるそうです。これらのうち2項目以上該当すればほぼ確実だそうです。森川将行先生によりますと、レビー小体型認知症で気をつけないといけないのは、レビー小体型認知症の始まりの多くは「もの忘れ以外」の症状であることだそうです。つまりレビー小体型認知症の進み方は、早い時期に現れやすい症状として幻視、誤認、パーキンソン症状、レム睡眠行動障害、うつなどで、認知機能の変動や低下はあとから出てくるそうです。 アルツハイマー病における危険因子として糖尿病、中年期の高血圧症、中年期の肥満、喫煙、うつ病、低い教育成績、身体的不活発などが報告されており、これら7つの全ての危険因子を10~25%減少させると世界中の110~300万人のケースを防ぐことができる可能性があると報告されています。 森川将行先生によりますと、認知症の予防や進行を遅らせるためにできることは禁煙、適度な飲酒、身体疾患の管理(生活習慣病の予防)、炎症反応を抑える、食生活(果実などビタミン類、野菜、魚、水分)、社会環境要因(ストレス対処行動、余暇活動)、学習・認知機能訓練、有酸素運動、十分な睡眠(適度な午睡)などだそうです。森川将行先生が認知機能の進行を遅らせるために日常外来で勧めていることは脂質、総カロリーの過剰な摂取を抑える、身体の病気は確実に治療、野菜・果実摂取、魚摂取、十分な水分摂取、適量のアルコール飲料、緑茶、大豆、カレースパイスなど、運動と余暇活動、頭の訓練(速い計算、文章を音読)などだそうです。ストレスに注意して、笑いを忘れずに、ということが重要だそうです。そして介護を全て家族で抱え込まない、介護保険を上手に利用し、家族の健康が本人の幸せだということでした。 森川将行先生は奈良医大出身で、私とも近い学年になります。それまで面識はありませんでしたが、奈良医大出身の先生が活躍しておられる姿を見せてもらって大変嬉しく思いました。 |

「アマゾンのサバイバル」
2015年06月07日(日) 院長ブログ
|
科学漫画サバイバルシリーズの「アマゾンのサバイバル」をクリニックの本棚に置きました。本屋さんに山積みしていました。世界各国でよく売れているそうです。 用語解説があって、勉強にもなりそうですね! |

「運を呼び込む神様ごはん」
2015年05月31日(日) 院長ブログ
|
「開運料理人ちこ」著の「運を呼び込む神様ごはん」を読みました。 不幸のどん底だったときに、塾の先生が握ってくれた塩おむすびを食べて感動したことをきっかけに運を呼び込む飲食店を始めたそうです。日々、口にしているものがわれわれ自身の体を作っているものですので食の大切さは言うまでもありませんが、食に関しては日々の生活において慣れによってなおざりになりがちです。そこをこれだけ突き詰めて、昇華させることは素晴らしいことと感じました。 味覚は舌の表面にある味蕾の中にある味細胞に食べ物の中に含まれる物質が作用して生じる電気が神経を通って脳に伝わり味を認識するという仕組みだそうです。このように味はバーチャル(仮想的)なものですが、自分の置かれた状況によっても味覚は変わるそうです。しかしながら感覚が人工的に作られても、それでも変わらない感覚の遙か彼方にある「意思」に働きかける「ごはん」を伝えたいと「ちこ」さんは言います。 「ちこ」さんはさまざまな料理を通して、出会う人たちに無条件の愛を実践し、絶対的な幸福の日々を送りたいと思っており、これが私のゴールであると言っておられます。これは大変価値の高い人生のミッションを掲げておられると思いました。 |

ラグビー日本代表の応援キャラクターに「アトム」
2015年05月29日(金) 院長ブログ
|
先月に日本ラグビー協会が2015年9月にイングランドで行われるラグビーワールドカップ2015に出場するラグビー日本代表の応援キャラクターに手塚治虫原作の漫画、「鉄腕アトム」の主人公である「アトム」が決定したことを発表しました。ラグビー日本代表初の応援キャラクターとなるアトムは、国内で行われる日本代表戦の試合会場にも応援に駆け付ける予定のほか、日本代表チームの活動や活躍をより多くの方に周知することを目的に、様々な形で日本代表応援キャラクターとして登場する予定だそうです。 「鉄腕アトム」は1963年に日本初となる30分枠のテレビアニメシリーズとして始まったそうです。1963年は私の生まれ年で、幼い頃に「鉄腕アトム」を白黒テレビで観たような気がします。 ラグビー日本代表選手は常人とはかけ離れた体格の人が多いですが、それでも外国チームの選手と比べると最も小柄な部類になるでしょう。「アトム」のように体は小さくとも100万馬力で活躍されることを期待したいです。そして「鉄腕アトム」にあやかってラグビー日本代表の知名度、人気が上昇することを願っています。 |

ためしてガッテン
2015年05月28日(木) 院長ブログ
|
5月13日放送の「ためしてガッテン」は、「驚き!最新ねんざ治療「3日安静」の大誤解」でした。 「足首のねんざ」はとてもありふれたケガで、多くの人が経験あることと思います。しかしながら「足首のねんざ」は実は靱帯損傷である場合が多く、放置すれば後遺症を残す場合もあります。骨折ではないので、比較的短期間で痛みが改善してしまうことも油断してしまう原因かもしれません。 番組では慶応義塾大学スポーツ医学研究センター准教授橋本健史先生がねんざした場合の治療法などを、奈良県立医科大学整形外科学教授田中康仁先生がねんざ対策予防として腓骨筋群の鍛え方を紹介されました。ねんざの治療では、じん帯を修復するコラーゲンが増えるまで約2週間は適切な固定をする必要があるということでした。腓骨筋群は緩んだじん帯をカバーすることのできる筋肉で、ねんざの再発や変形性足関節症の予防にもつながります。 実は、私は番組をリアルタイムでは視られなかったのですが、先週に「テレビを観て…、足が心配になって…。」と来られた方が何名もおられました。その方々に「ためしてガッテン」ですか?と聞きますと、皆「そうです!」とのお答え。大変、影響力の強い番組ですね! |