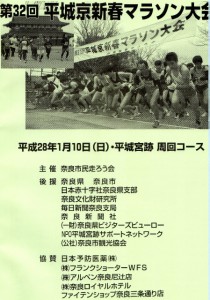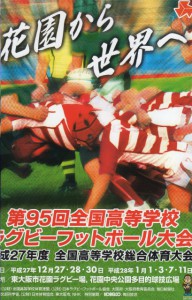三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


第32回平城京新春マラソン大会
2016年01月10日(日) 院長ブログ
|
今日、第32回平城京新春マラソン大会が開催されました。妻と一緒に10kmの部に出場しました。 この大会の参加は今回が初めてです。32回も続いているとは、歴史のある大会ですね。今日は素晴らしい天気で、マラソン日和でした。 本大会は小学生が2.5kmの部、中学生以上と大人は5kmと10kmの部に分かれています。平城京跡周回コース2.5kmを10kmの部の場合は4周走ります。10kmの部は男女合わせて904人の参加で、私はほぼ最後尾からゆっくりと走っていましたら1周過ぎたところで先頭の選手に抜かされてしまいました。この後少しはペースを上げましたが、準備不足もたたって先頭の選手には最後の方にはなんと2回も抜かされてしまいました。たった4周のレースで2周の周回遅れって…、先頭の選手に感心するやら、自分の不甲斐なさに落胆するやら…、でした。 平城京跡は今まで行ったことがなかったのですが、近鉄西大寺駅から徒歩10分足らずと非常に便利なところにあります。平城京跡周回コースはとても走りやすいコースですが、街灯もあまりなさそうでしたので時間が遅くて暗いとジョギングはできなさそうでした。本大会は「奈良走ろう会」主催ということでしたが、手作りのアットホームな感じがよかったです。ボランティアの方も名簿で見て、直接名前を呼んで応援してくれたりしていました。 今度はもう少し準備して、また参加したいと思いました。 |

今日は準々決勝
2016年01月03日(日) 院長ブログ
|
第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会も今日は準々決勝です。本日も医務委員として参加しました。 今日はベストエイトの激突、しかも地元近畿勢が5チームも勝ち上がっているということもあり、今までに見たことがないくらい観客席が大勢の観客の方で一杯でした。メインスタンド、バックスタンドはもちろんのことゴールポスト側のサイドスタンドまで一杯になっていました。好天と最近のラグビー人気が後押ししたのかもしれません。それにしても今年の正月は暖かいですね。12月30日といい今日といい、いつもの花園の全国大会では考えられないほどのポカポカ陽気でした。本当に暖冬ですね。 今日は、全ての試合が第1グラウンドで行われました。第4試合の大阪第二地区代表大阪桐蔭高校と福岡県代表東福岡高校の試合はとてもハイレベルで熱戦となりました。両チームともFWの選手は高校生とは思えないほどの立派な体格で、FWのぶつかり合いも迫力満点でした。BKの選手もスピード、スキルともに優れており終盤まで拮抗した試合展開でしたが、最後は東福岡高校が押し切りました。本当に素晴らしい試合でした。両チームの選手に心から拍手を送りたいです。 例年ですと、この後1月5日に準決勝、1月7日に決勝というスケジュールですが、今年は少し間が空いて1月7日に準決勝、1月11日に決勝というスケジュールです。今までは高校生の冬休み期間に合わせた試合日程であったのでしょうが、1日おきに試合が5試合も6試合も続くのはやはり無理があると思われます。これだけ激しい試合をしている選手の体がそんなに短期間に回復しているとは思えません。将来ある選手たちのケガのことも心配です。選手の体を第一に考えたスケジュールを願わずにはおれません。 |

謹賀新年
2016年01月01日(金) 院長ブログ
|
皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 来月には開院5周年を迎えます。節目の年を迎え、なお一層医療サービスの質と患者さま満足度の両方を向上させることを成し遂げたいという思いで一杯です。皆様の健康増進と生活の質の向上に寄与できましたら、これほど嬉しいことはないと思っております。 今年1年も、皆様にとりまして素晴らしい1年でありますことを願っております。
秋山整形外科クリニック院長 秋山晃一 |

第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会
2015年12月30日(水) 院長ブログ
|
本日、東大阪市花園ラグビー場、花園中央公園多目的球技広場で第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会第3日が開催されました。医務委員として参加しました。 今朝は冷え込みが強く随分寒くなるのではと心配しましたが、天候は素晴らしく気温も上がって絶好のラグビー日和でした。今日は第3グラウンド担当でしたので朝の9時頃から6試合連続で夕方4時過ぎまでの観戦となりました。いつも6試合連続ともなると生駒おろしの木枯らしで凍えるのですが、穏やかな気候のお陰で快適に観戦することができました。 大会は今日からシード校も出場しますし試合数も最も多い日ですので、会場も更に活気を帯びてきています。 今日の第3グラウンド最後の試合は大阪第3地区代表常翔学園高校と奈良県代表天理高校の試合でした。大阪と奈良の地元近畿勢同士の試合ということもあって観客もとても多く、全ての方が観客席に座って観戦することがとても困難な状況でした。第3グラウンドは、天然芝は見事に美しいのですが陸上トラックがあることと観客席が狭いことが難点です。今まで見たことがないくらい観客が一杯で観客席横の土手にも沢山座ってみておられるような状況でした。この試合は素晴らしい熱戦でしたので、もっと観客の方がいい環境で観戦できればよいのにと思わずにはおれませんでした。 この試合は本当にハイレベルな試合でした。シード校である常翔学園高校の猛攻をノートライに抑えて、WTBの選手の見事なステップで1トライを挙げた天理高校が勝利しました。両チームともにディフェンスの能力が高くてロースコアでも、とてもスリリングな展開で見応えのある試合でした。両チームは伝統のあるチームで、ユニフォームの柄も昔のままです。ラグビージャージも昔は綿の重いけれどあまり温くない素材の長袖でしたが、今は吸湿性も優れて柔らかく着心地のよい素材の半袖に替わっています。ジャージの素材は変わっても常翔学園高校は大阪工大高の頃から紺色に胸に2本の赤いラインのユニフォーム、天理高校はジャージ、短パン、ストッキングに至るまで真っ白のユニフォームで、共に一般に認知度も高く、大変多くの方に親しまれているユニフォームであると思われます。伝統のユニフォームが受け継がれるのって本当にいいですね。日本代表チームのユニフォームも昔ながらの赤白の段柄に戻ったタイミングで活躍し脚光を浴びて、個人的にはすごくよかったのではないかと思っています。 |

2015年度日本プロスポーツ大賞
2015年12月27日(日) 院長ブログ
|
昨日、2015年度内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞の授賞式が行われたという報道がありました。「ラグビー日本代表」がラグビーワールドカップイングランド大会1次リーグで強豪南アフリカ代表に勝利し、史上最多の3勝を挙げたことを評価され大賞を受賞したということでした。おめでとうございます。 日本代表のワールドカップでの活躍により、ラグビーが今までになく注目されているようです。トップリーグの観客数も増加しているようで、今日の東芝―サントリー戦はトップリーグ歴代最多であったそうです。また先日、2016年度シーズンからスーパーラグビーに参加する日本のチーム「サンウルブズ」の発表もありました。この、かつて経験のない追い風にラグビー界全体が乗って行けたらいいですね!
|