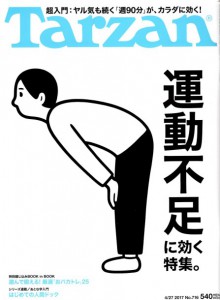三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


「がん診療と地域連携~肺がん治療を中心に~」
2017年05月03日(水) 院長ブログ
|
先日、名賀医師会臨床懇話会が開催されました。特別講演は「がん診療と地域連携~肺がん治療を中心に~」で講師は伊賀市立上野総合市民病院副院長田中基幹先生でした。田中基幹先生は泌尿器科と腫瘍内科を専門としておられ、泌尿器科領域にとどまらず全ての領域のがん診療に取り組んでおられます。田中基幹先生は伊賀市立上野総合市民病院におけるがん診療と地域連携について紹介してくださいました。 田中基幹先生によりますと日本人の2人に1人は癌にかかり、3人に1人は癌で亡くなるそうです。今や日本は癌多死社会と言える、ということでした。日本人が罹患する癌の頻度は大腸癌、胃癌、肺癌などが多いそうですが、肺癌は死亡数が多く、発見が遅れると死亡率が高くなるということでした。田中基幹先生によりますとこれからのがん診療で求められることは、ライフステージや癌の特性を考慮した個別化医療であるだろうということでした。 伊賀地域二次救急医療圏(伊賀市、名張市および周辺地域)における人口は約18万人、高齢者は約5万人であるそうです。伊賀地域二次救急実施病院は伊賀市立上野総合市民病院、岡波総合病院、名張市立病院の3病院だけですので、一定の割合で他地域への患者さんの流出はあると思われます。田中基幹先生はできるだけ多くの方が、慣れ親しんだ地域で医療を完結できるように目指したいと言っておられました。 田中基幹先生は泌尿器科専門医だけでなく、日本がん治療認定医、日本がん検診・診断認定医なども持っておられ、伊賀市立上野総合市民病院では本館5階の地域集学治療センターを立ち上げ統括しておられるようです。こちらは50床で4人部屋6室と個室が20室もあるそうで、入院患者様のQOLとプライバシーに配慮されています。がんサポート・免疫栄養療法センターではがん化学療法認定看護師や日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医など各種エキスパートの育成を進め、外来化学療法室を運用し通院での化学療法を推進しているということでした。医師(がん治療認定医・精神科医)、看護師、栄養士、がん相談支援室スタッフなど多職種により緩和ケアチームを作っているそうです。免疫栄養療法を含めた適切な栄養療法を介入することでがん患者の体重減少とQOLの低下、生命予後まで改善されるということで免疫栄養療法室が役割を果たしているそうです。 伊賀市立上野総合市民病院は在宅療養後方支援病院として開業医との連携強化を図っているそうです。かかりつけ医との連携も強化しており、退院後のフォローにも力を入れているそうです。伊賀市立上野総合市民病院では地域出前講座や市民講座を行い、地域住民との交流も積極的に深めているそうです。地域医療研修会も活発で、がん診療連携推進病院指定を受けている伊賀市立上野総合市民病院では毎月1回多職種の医療スタッフが参集し「キャンサーボード」という検討会、講習会を開催しているそうです。これらの取り組みにより、紹介率、逆紹介率も向上してきているそうです。 地域集学治療センターでは手術を受けられた患者様だけではなく、他病院で治療を受けられた患者様のがん治療継続、緩和医療や終末期医療を紹介元や地域医療機関と連携し後方支援を中心に運用するという役割であるそうです。伊賀市立上野総合市民病院におきまして着実に進んだ医療システムが構築されてきている様子と、それを牽引している田中基幹先生の熱意に感心いたしました。 |

管理栄養士
2017年04月30日(日) 院長ブログ
|
天理大学ラグビー部の食事指導をしている管理栄養士である岡田あき子さんの記事が4月25日の毎日新聞に掲載されていました。 岡田あき子さんはフリーの管理栄養士として活躍しておられ、週に1度は天理大学ラグビー寮に通っておられ140名を超える部員の食生活指導を行っておられます。部員たちも体が資本ですから、本当に心強い限りだと思います。 岡田あき子さんは「Sports diet」を立ち上げて、栄養セミナー講師、スポーツ栄養、チームサポート、パーソナル栄養指導、食アスリート協会公認講座など幅広い活動をしておられます。 岡田あき子さんの場合は自らがマラソンランナーなので、アスリートにとっても説得力が強いと思います。天理大学で岡田あき子さんに伺いましたが、普段のランニング量が半端ないです!なんと言ってもフルマラソンのサブスリーですからね。レベルが違いますね! |

Tarzan
2017年04月25日(火) 院長ブログ
|
今月号のTarzanは「運動不足に効く特集」であったので、購入しました。 最近、本当に運動不足です。運動せねばと痛感します。本書には喫煙と肥満により、健康だけでなく生涯に必要な医療費まで変わってしまうというデータも掲載されていました。 中に載っていた春のBaka training college special…、バカバカしいけどちょっと笑えます。 |

Familie*
2017年04月23日(日) 院長ブログ
|
先日、クリニックの待合室に飾るお花がファミーリエから届きました。 ファミーリエは名張市にある花屋さんで、以前からよく利用させていただいております。いつも期待以上の出来映えにしていただき、大変満足しています。今回、皆様に癒やしを感じていただけるような、季節を彩るお花をお願いいたしました。 今まではプリザーブドフラワーを注文することが多かったのですが、今回はアーティフィシャルフラワーです。(ですね?片芝さん。) 皆様、是非ご覧下さい。 |

第4回馬見チューリップフェア
2017年04月09日(日) 院長ブログ
|
馬見丘陵公園で「やまと花ごよみ2017」第4回馬見チューリップフェアが開催されており、昼から雨も上がったので見に行ってきました。 チューリップと満開の桜のコラボで、とても綺麗でした。大勢の人で賑わっており、駐車場も満車の様子でした。 大道芸パフォーマンスやNHK奈良合唱団のステージもやっていました。 雨が上がってくれて、本当に良かったです!
|