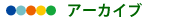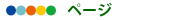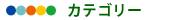三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


「日本人はなぜ日本のことを知らないのか」
2017年10月29日(日) 院長ブログ
|
先日、竹田恒泰氏の「日本人はなぜ日本のことを知らないのか」という講演会を聴きました。 竹田恒泰氏は旧皇族・竹田家の生まれで明治天皇の玄孫にあたるそうです。今回の記念講演は名張ロータリークラブ創立55周年記念事業で、同日午前には名張市夏見の「夏見廃寺跡」の昌福寺案内板寄贈記念式典も開催されたそうです。右派政治評論家として鳴らす竹田恒泰氏ですが、テレビ番組の「そこまで言って委員会NP」などで時々見かける(私はあまりテレビ番組自体を観ませんが…)舌鋒鋭い論戦さながらの講演を大変興味深く拝聴いたしました。そして1時間以上にわたる独演会、やはり引き込まれるものがありとても面白かったです。喋り口調は思ったよりソフトで、その内容から竹田恒泰氏の日本愛を強く感じました。 海外に留学した学生が口々に「日本のことを知らなさ過ぎて恥ずかしい。」と言うそうですが、確かにもし外国人に日本のことを尋ねられたら果たして自分が何を答えられるのだろうと思うとドッキリしました。何十年も前ですが小学校・中学校・高校で日本の歴史を学んだのに…、と情けなく思いました。私の記憶力の問題かもしれませんが…。 「目から鱗」の話も多く、日本の歴史をもっと知りたいと思いました。そしてまた機会があれば竹田恒泰氏の講演をもう一度聴いてみたいものだと思いました。 |

Familie*
2017年10月21日(土) 院長ブログ
|
先日届いた、今季のFamilie*のお花は秋色の爽やかな雰囲気で、とっても素敵です。
それにしても、先日来の長雨の影響で、一気に秋が深まった感じですね。
明日から明後日にかけて台風21号の猛威が心配です。月曜日の朝が特に心配ですね。 |

第7回馬見フラワーフェスタ
2017年10月09日(月) 院長ブログ
|
本日、やまと花ごよみ2017第7回馬見フラワーフェスタ、奈良フードフェスティバル2017シェフェスタ in 馬見を見に馬見丘陵公園に行ってきました。フードフェスティバルも人気で好天も相まって、来場者で大賑わいでした。 恒例のダリア花じゅうたんをはじめ、馬見花苑ではサルビア、マリーゴールド、ペチュニアなど美しい花々が咲き誇っていました。ダリア園も圧巻です。 また恒例の大道芸パフォーマンスやジャズ音楽の演奏も行われていました。 秋の花は楽しめましたが、今日の暑さはまるで夏ですね。先週までの涼しさがウソのようです。歩き回って、いい汗をかけました。 |

「外来診療に役立つ手外科疾患の診断と治療」
2017年10月08日(日) 院長ブログ
|
先日、三重学術講演会が開催されました。特別講演は「外来診療に役立つ手外科疾患の診断と治療」で講師は鈴鹿回生病院整形外科副院長森田哲正先生でした。森田哲正先生は「ばね指」、「手根管症候群」、「デュピュイトラン拘縮」という外来でしばしば見かける3疾患に関して解説して下さいました。 「ばね指(腱鞘炎)」は指の屈筋腱の腱鞘炎で、しばしば見かける疾患です。腱鞘炎が進行すると引っかかりを生じばね減少が起こるとばね指と呼ばれます。使いすぎによる負荷のために起こるので固定などの局所の安静が推奨されることが多いのですが、森田哲正先生はむしろ少々痛みがあっても、腱は動かした方が良いと勧めておられました。森田哲正先生は保存治療の一つとしてトリアムシノロン腱鞘内注射を積極的に施行しているということでした。トリアムシノロン5mgに0.5%キシロカイン1mlを混ぜたものを注射しているということでしたが、糖尿病の方でも糖尿病の治療コントロールが良ければ施行しているということでした。トリアムシノロン腱鞘内注射の後は、痛くても20回自動他動運動をすることが大事であるということでした。注射は少なくとも3ヶ月間は間を開けるということで、手術治療は患者様が希望されれば行うということでした。森田哲正先生のデータによりますと、1回の注射のみで治癒したのは57.8%であったそうです。すなわち約42%に再発を認め、注射回数は平均3.2回、再注射までの期間は平均7.1ヶ月間であったそうです。保存治療から手術治療に至る理由としては、手術治療の方が確実であるからという理由が1番多く、次に注射自体の痛みであるそうです。「ばね指(腱鞘炎)」が難治性になる因子として、多数指罹患、糖尿病、手根管症候群の合併、罹病期間が長い、関節リウマチなどが挙げられるそうです。トリアムシノロン腱鞘内注射の注意点として腱鞘内になるべく入れる、皮下に漏らさないことを挙げられました。これはトリアムシノロンが皮下に漏れると白斑や脂肪萎縮の合併症をきたすことがあるからということでした。 「手根管症候群」は75歳以上の高齢者の手根管症候群が増加しているそうです。高齢者の手根管症候群の特徴として、重症例が多く術後も知覚や筋力の回復は不十分であるものの、自覚症状は改善するので手術治療も勧められるということでした。術前に母指対立不能では対立再建も同時に行うそうです。 「デュピュイトラン拘縮」は比較的まれな疾患と思っておりましたが、オランダやボスニアでは高齢者に非常に高率であり、日本でも高齢者には多いそうで、特に50歳代以降の男性に多く環指、小指に好発するそうです。手術治療の必要な場合は手掌腱膜切除術が選択されますが、神経・血管の損傷をしないように手外科専門医による治療を要します。この疾患のトピックスは手術治療に代わる酵素注射療法が開発されたことでしょうね。こちらも規定の講習を修了した手外科専門医のみが行うことができるということですが、手術治療なしで治療できるとは画期的です。森田哲正先生は酵素注射療法の症例について紹介してくださいました。デュピュイトラン拘縮は初期には手掌にしこりやくぼみを生じ、結節となり、更に指が曲がって伸びなくなるということです。平らなテーブルの上に手のひらを下にして置き、上から圧力をかけて手のひらをぴったりとつけられるかどうかを試して、テーブルと手のひらの間に隙間ができるかを確認する「テーブルトップテスト」により、隙間ができるようであれば治療が検討されます。手掌部の結節だけではなかなか患者様は受診されませんが、指が屈曲してくれば洗顔時に指先が目や鼻に当たったりするようになるので、指が屈曲してくればできるだけ早期に酵素注射療法などを考慮することが望ましいということでした。 森田哲正先生の講演はいつも明快でわかりやすく、とても参考になります。ありがとうございました。 |

第5回糖尿病を考える会 in 名張
2017年09月28日(木) 院長ブログ
|
先日、第5回糖尿病を考える会in名張が開催されました。特別講演は「患者さんのやる気を引き出す対話法~糖尿病コーチング~」で講師は佐世保中央病院糖尿病センター長松本一成先生でした。 コーチングに関しては、以前から興味はあったもののほとんど知識がなく、一度専門家の話を聞いてみたいものだと思っておりました。私が糖尿病の治療をすることはありませんが、森岡内科クリニック院長森岡浩平先生にコーチングの有名な先生が来るので、ということでお誘いいただき今回出席いたしました。森岡浩平先生もコーチングに詳しく、臨床で実践しておられます。今回大変有意義な会で、出席して本当によかったと思いました。 松本一成先生によりますと、コーチングとはクライアントが自らのゴールを設定し、それに向かって行動を起こすことを目的とした特殊なコミュニケーション法であり、コーチは主に質問することにより上記を実行するということでした。基本理念は「人が必要とする答えは、その人の中に存在する」ということでした。私が持っている答えを教えてあげるというTeaching(ティーチング)とは異なり、あなたが持っている答えを一緒にさがそうというのがCoaching(コーチング)であるということでした。 松本一成先生によりますと、医療者は「患者さんの話をよく聴きなさい。」と指導されるが、よい聴き方とはどんな聴き方か?ということを教えてもらうことは少ないということでした。これは成る程と思われるところでした。確かに、よい聴き方とはどんな聴き方か?ということを指導してくれる人にはあまり出会ったことがありません。松本一成先生によりますとコーチングのスキルとしてのよい聴き方とは、①話すよりも聴くことに時間を割く、②批判をしない、判断もしない(ゼロポジション)、③聴いているというサインを送る、④視線はやわらかく相手に合わせる、⑤最後まで聴く、途中で口を挟まない、⑥どう答えるかは、相手が話し終えてから考える、⑦沈黙を受け入れる、⑧辛抱強くなる、⑨相手の結論を先取りしない、などであるそうです。医師は患者の話を根気強く聴くことが苦手であるそうで、約20秒で口を挟むという報告があるそうです。 松本一成先生によりますと「ゼロポジション」とは相手の話をサマライズできるように集中して聴く態度であるそうです。話し手が自分の言葉で話してみて、自分の考えを確認することをオートクラインというそうです。聞き手が話し手の話を聴いた後で、話し手にサマリーを返すことをサマリー返しというそうで、オートクラインとサマリー返しにより話し手の行動は促進するそうです。 松本一成先生によりますと「頷きと相づち」も重要であるということでした。対話中に温かい頷きと相づちをできるだけたくさん入れることで、「あなたの話をもっと聞かせて」というメッセージを送るそうです。「オウム返し」は相手の語尾を繰り返すことで「あなたの話を受け止めています」というメッセージを送れるということでした。 松本一成先生によりますとコーチングは「質問型コミュニケーション」とも呼ばれるそうです。「どう思いますか?」「どう考えますか?」といった質問の仕方はオープン型質問といい、相手が自分の言葉で話そうとするために話題や情報を得られやすいそうです。これからのことを聞く未来型質問はクライアントのレパートリーの中からアイデアを出してもらう質問で、面接の終わり際に使うと有効であるということでした。 松本一成先生は行動変容を目的とした4つの質問パターンとして①現状維持の不利益、②変わることの利益、③変化に対する楽観性、④変化の決断の4種類を提示して下さいました。 松本一成先生によりますと漠然とした言葉の塊を、聞き返しによってほぐしていくことも有効であるということでした。クライアントの考えをできるだけ正確に言葉で表すことが「共感する」ことに繋がるそうで、松本一成先生によりますと、そのためには「聞き返し」で確認することだそうです。同情や同感ではなく、共感的理解が行動を変えるそうです。このあたりはちょっと理解の難しいところですね。ともすると共感と同情や同感を取り違えてしまいそうです。そしてなんと、共感が高い主治医であれば、その糖尿病患者の治療成績がよいという報告もあるそうです。 松本一成先生によりますと「承認する」ことも大事なコーチングの基本スキルであるということです。「承認する」ことは「私はあなたの味方です。」と言っていることと同じで、承認されると自己効力感が高まるそうです。時間を置かずに承認することで結果として行動が増えるそうで、オペラント条件づけと言うそうです。松本一成先生によりますと承認の仕方も、客観的な事実を承認するYouメッセージと主観的な影響を伝えるIメッセージで承認することが重要であるそうです。特にIメッセージで承認することが重要であるということでした。 松本一成先生によりますと「言った」・「聞いていない」というトラブルは医療業界ではよくあることで、確実に伝えるための方法として2つのスキルを紹介してくださいました。一つは「枕詞で許可を取る」ということで、相手に許可を求める枕詞を使うと、その後のメッセージのとおりが非常によくなるということです。もう一つは「情報提供」で「相手によって内容や順序を変える」すなわち個別対応が重要であるということでした。 松本一成先生はコーチングフローとして4 Stepモデルを紹介してくださいました。これは①現状の明確化、②ギャップの明確化、③具体的な行動目標の設定、④考え得る障害と対策からなります。 松本一成先生は佐世保中央病院におけるコーチングを用いた栄養看護外来を紹介してくださいました。看護師、栄養士、医師、他職種との協働チーム医療であり、患者様の自主性を重んじているそうです。診察の流れは、予約患者さんの受診、体重・血圧のセルフチェック、採血・採尿、栄養看護外来(検査結果報告とコーチング・情報提供)、医師診察、会計、だそうです。栄養看護外来に際しての注意事項は、①「感情を聴くこと」を最優先とする。②検査結果そのものよりも、行動に焦点を当てる。③断定的な言い方「良い」「悪い」などは安易に使わない。④「患者さんの抵抗」には抵抗しない。⑤機が熟していないときには、目標設定まで持って行こうとしない。だそうです。 栄養看護外来の特徴は①当日の検査結果をすべての患者に報告(リアルタイム)。②チームでコーチングを行い、患者もチームの一員として自己管理できるように支援。③患者自身による活きた行動目標の設定(可能な場合)。④栄養士(主に食事療法担当)と看護師(薬物やフットケアなど担当)が得意分野の知識を共有。⑤コ・メディカルから医師へバトンをつなぐ分担制診療。などであるそうです。 栄養看護外来のアウトカムとして高頻度に見られるのは行動変容、HbA1cの改善などであるそうです。コーチングはまさに糖尿病診療にうってつけの方法ですね。いや、糖尿病の治療だけではなく、診療全体に用いられて活用されるべき手法であると思われました。私にとってコーチングの話は大変興味深く思われ、今後更にコーチングについて学んでみたいものだと思いました。 |