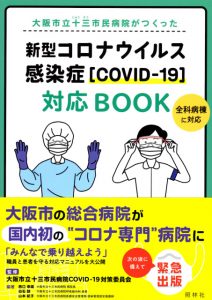三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


第57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝
2021年01月11日(月) 院長ブログ
|
本日、第57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝が国立競技場で行われました。グラウンドドクターとして参加させていただきました。 結果は天理大学が早稲田大学に55-28で勝利しました。 歴史的瞬間に立ち会うことができて、感激しています。 本当にありがとうございました。 |

新年あけましておめでとうございます。
2021年01月01日(金) 院長ブログ
|
あけましておめでとうございます。 旧年中は大変お世話になりました。
昨年はコロナ禍で世界中が影響を受けた1年でした。 今年は、コロナ禍の収束を願いつつ、より感染予防に取り組んでいきたいと思っております。さらに日常診療の充実を目指したいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 |



「十三市民病院におけるCOVID-19診療」
2020年11月23日(月) 院長ブログ
|
本日、ある会議にオンラインで参加し、「十三市民病院におけるCOVID-19診療」という講演を拝聴いたしました。演者は十三市民病院呼吸器内科部長白石訓先生でした。 現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の第3波が到来していると言われており、全国の1日の新規陽性者数が更新されている今日この頃、とても貴重なご講演を聞かせていただきました。 大阪市立十三市民病院では2020年3月23日から結核病棟を新型コロナウイルス感染症対応病棟として、感染患者の受け入れを実施していたそうです。2020年4月14日に大阪市長松井一郎氏は「大阪市立十三市民病院を“コロナ専門病院”にします。」と宣言したことを受け、2020年5月1日から新型コロナウイルス感染症中等度患者の入院専門病院になったそうです。 COVID-19の重症度分類では、軽症は呼吸器症状がなく咳のみで息切れもなくSpO2が96%以上で、入院も必要ない場合が多いそうです。重症とはICUに入院したり、人工呼吸器が必要であったりする場合であるそうです。大阪市立十三市民病院では肺炎所見や息切れもあるが、基本的には酸素投与の必要ない中等症の症例が入院対象となっているそうです。 COVID-19患者を集めて隔離する場合には、非清潔区域と清潔区域を明確に区分けする必要があるということで、陽性(レッド)ゾーン、前室(イエロー)ゾーン、清潔(グリーン)ゾーンに分けるゾーニングを行ったそうです。 COVID-19患者の特徴としては、喫煙歴のある場合や糖尿病患者が高率であるそうですが、糖尿病のコントロール不良の場合予後が不良である場合が多いということです。男女比は中等症では男性がやや多い傾向ですが、大阪市立十三市民病院から高次医療センターに転院となる重症例では男性の方が圧倒的に多いそうです。重症例になると、肺血栓症、肺塞栓症などを生じてくる場合が多く、呼吸器内科だけでの対応は困難になることもあるということでした。酸素療法の考え方として、目標はSpO2が93~96%に維持することを目標とし、維持できない場合は酸素投与を徐々に増やしていき、転院できない場合は挿管も考慮するということでした。 医療従事者の曝露のリスク評価と対応では、患者がマスクを着用していない場合には、医療従事者が高度のPPE(個人防護具)をしていないと濃厚接触者となり就業制限を要する場合があるので、患者と医療従事者の両者がマスクの着用をしていることが重要であるということでした。 現在はCOVID-19患者重傷者数の増加により、医療提供体制が逼迫してきているそうです。大阪市でCOVID-19診療の中核を担っている大阪市立十三市民病院の責任の重さがうかがい知れました。大変勉強になりました。白石訓先生、ありがとうございました。 |