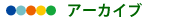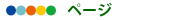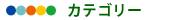三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ


「最新のエビデンスから考える骨粗鬆症治療薬の使い分け」
2017年09月10日(日) 院長ブログ
|
先日、名賀医師会臨床懇話会が開催されました。特別講演は「最新のエビデンスから考える骨粗鬆症治療薬の使い分け」で講師は三重大学大学院医学系研究科運動器外科学・腫瘍集学治療学教授須藤啓広教授でした。 骨粗鬆症治療薬は最近、多く開発されて治療の選択肢が多くなってきました。須藤啓広教授は最新のエビデンスに基づいて、骨粗鬆症治療薬の使い分けをわかりやすく解説して下さいました。 須藤啓広教授はまず、脆弱性骨折である大腿骨近位部骨折は全例骨粗鬆症であり骨粗鬆症薬物治療の適応であるということを強調されました。これは大腿骨近位部骨折の治療後であっても、骨粗鬆症薬物治療が継続されずに終わってしまう例が多いということなどが背景にあると思われます。須藤啓広教授は大腿骨近位部骨折後に適切な骨粗鬆症治療がなされないと生存率が低下し生命予後が悪化すること、大腿骨近位部骨折後に反対側を再び受傷することが多く脆弱性骨折は骨折の連鎖を起こすこと、両側の大腿骨近位部骨折を起こすと生存率がさらに低下し、予後が悪化することなどを理由として挙げられました。 それでは、どの薬剤を選択するかですが、須藤啓広教授はエビデンスから考えると有効性の評価Aであるビスホスホネート薬(アレンドロン酸、リセドロン酸)、デノスマブ、ゾレドロン酸から選ぶのが合理的であると述べられました。75歳以上の人に対する大腿骨近位部骨折抑制効果はデノスマブで有効性が認められているそうです。骨折部の骨癒合に対する骨粗鬆症治療薬の影響は、ビスホスホネート薬、デノスマブでも臨床的には骨癒合への悪影響は報告されていないということでした。 須藤啓広教授は次に脆弱性骨折である椎体骨折は骨粗鬆症であり、骨粗鬆症薬物治療の適応であるということを強調されました。椎体骨折は単純レントゲン写真にて新鮮例か陳旧例か判別しにくい例をしばしば認めます。須藤啓広教授は座位と立位のレントゲン写真を比較することにより、椎体骨折が新鮮例か陳旧例かの診断精度が上がるデータを示されました。椎体骨折症例に対して適切な骨粗鬆症薬物治療がなされないと生命予後が悪化し、特に椎体骨折を三カ所以上起こしていると有意に生存率が低下するそうです。椎体骨折に対して有効性の評価Aである骨粗鬆症薬物治療はエルデカルシトール、ビスホスホネート薬(アレンドロン酸、リセドロン酸、ミノドロン酸、イバンドロン酸)、SERM(ラロキシフェン、バセドキシフェン)、副甲状腺ホルモン薬(テリパラチド遺伝子組換え、テリパラチド酢酸塩)、デノスマブです。副甲状腺ホルモン薬は骨折の危険性の高い骨粗鬆症に適応されるということです。 須藤啓広教授によりますと、生命予後の悪化につながる骨折の連鎖を絶つためには、まず骨密度検査を積極的に行うこと、必要に応じて胸腰椎レントゲン検査をすることであると強調されました。椎体骨折の約3分の1は無症状であるということですので、疼痛がなくても身長低下や脊椎変形の疑われる症例には胸腰椎レントゲン検査が必要ですね。 骨粗鬆症治療薬では薬物により報告されている骨密度増加割合は様々です。須藤啓広教授は「Goal-Directed Treatment for Osteoporosis」ということを紹介してくださいました。これは元々の骨密度から約3~5年で薬物治療を行うことにより目標とする骨密度に達するように、骨密度増加効果別に薬剤選択を考えるということです。これによりますと骨密度低下の著明な場合には骨密度増加割合の大きい副甲状腺ホルモン薬、デノスマブ、ビスホスホネート薬などからの選択が望ましいということでした。副甲状腺ホルモン薬(テリパラチド遺伝子組換え)からデノスマブへの逐次療法で大幅な骨量増加が得られたそうです。これは順序が大事で、骨形成促進剤投与後に骨吸収抑制剤投与することが有効であるということでした。副甲状腺ホルモン薬(テリパラチド酢酸塩)からデノスマブまたはビスホスホネート薬へのスイッチではデノスマブの方が有意に骨量増加し背部痛減少したというデータがあるそうです。しかしながらデノスマブ中止後に1年間で骨密度減少を認め、脆弱性骨折の危険性が増加したということで注意を要するようです。 須藤啓広教授は整形外科のみならず他科の診療所においても、骨粗鬆症治療を必要とする方に確実に薬物治療がなされることの重要性を説かれ、薬物治療薬の使い分けをガイドラインに沿って大変わかりやすく解説して下さいました。 |