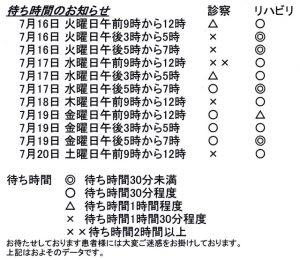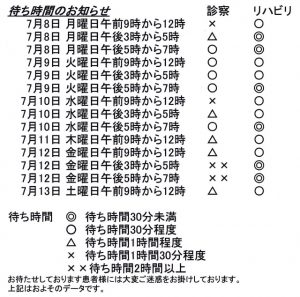リハビリ通信 No.299 筋の起始と停止について
2019年07月21日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
筋肉は筋収縮したり伸張されたりする組織であり、この筋肉が骨(軟部組織に付着を持つ筋もある)のどこに付着しているかで作用(動き)が決まります。この付着部の両端のことをそれぞれ「起始」と「停止」といいます。また、筋肉の筋線維はこの起始と停止の方向に向かって走行しており、筋線維方向に収縮と伸張が生じます。 我々理学療法士が運動療法を行う際、筋の起始と停止が非常に重要となってきます。例えば、一つの筋肉をストレッチする際、最も起始と停止が遠ざかるポジションにしながら筋肉を伸張しなければなりません。また、筋肉を収縮させる際も起始と停止が近づく運動(求心性収縮と言います)を促さなければなりません。そのため、起始と停止はもちろんのこと、筋肉の線維方向もイメージしながら運動療法を行っています。 リハビリテーション科 小野正博 |



夏期休業のお知らせ
2019年07月11日(木) クリニックインフォメーション1新着情報
|
当クリニックでは下記の期間を夏期休業とさせていただきますので、ご案内いたします。 休業期間は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、ご容赦くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
夏期休業期間 令和元年8月11日(日)~令和元年8月15日(木)
|

リハビリ通信 No.298 跛行について
2019年07月07日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
跛行とは何らかの障害により正常な歩行が出来ない状態の事を言います。歩行は片脚立位が交互に連続性を持って行われる動作で、視覚、平衡感覚、バランスなどの神経感覚と筋、骨、関節の動きなどが精密に連携して働き歩行と言う一連の動作を行います。 神経感覚、筋骨の何かに障害を受け、動作機能として働かない場合、正常な歩行はできず異常歩行つまり、跛行になります。跛行が起きる要因に疼痛の逃避性跛行、筋力低下による跛行、形態異常による跛行、中枢神経の障害による跛行があります。 代表的な跛行にトレンデレンブルグ跛行、デュシエンヌ跛行があります。筋力低下、変形、拘縮などの要因により見られます。 理学療法士は原因により改善できる場合、適切なアプローチを行い安定した歩行に近づける様に治療を進めて行きます。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |