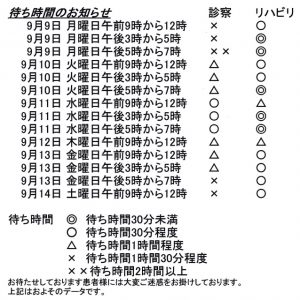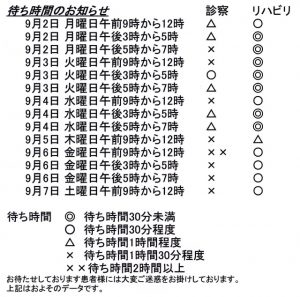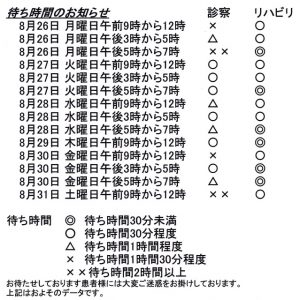リハビリ通信 No.303 肩関節周囲炎について
2019年09月19日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
|
当院にも肩関節周囲炎の患者様が多く来院されます。肩関節周囲炎と言うと聞き慣れない言葉かもしれませんが、俗名として「五十肩」と呼ばれるものがこれにあたります。 患者様との会話の中で、「私、50歳過ぎてるけど五十肩?」とか「70歳やから七十肩じゃないの?」といった質問があるので、これについてご紹介させていただきます。 今よりもっともっと平均寿命が短かった時代に「だいたい50歳代になると肩が痛くなる」ということから「五十肩」と呼ばれるようになったそうで、今の時代に照らし合わせると「七十肩」や「八十肩」と言うべきなのかもしれませんが、変わらずに俗名として「五十肩」と呼ばれているのが現状です。 この肩関節周囲炎は、骨に異常は無く、痛みや関節可動域の制限が生じ、日常生活動作を制限してしまうものです。「近所の人が放置してたら治るよって言ってたから病院には行かなかった。」という方も多大勢おられますが、放置して拘縮(関節が固まってしまう状態のこと)が完成されてしまうと非常に時間がかかってしまうこととなります。なので、肩関節で痛みを自覚されている方、可動域が制限されてきている方は受診することをお勧めします。 リハビリテーション科 小野正博 |

10月22日(火)休診のお知らせ
2019年09月15日(日) クリニックインフォメーション1新着情報
|
来たる10月22日は、「即位礼正殿の儀の行われる日」であり、「国民の祝日」ですので、クリニックは休診とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 |