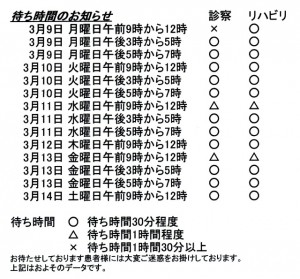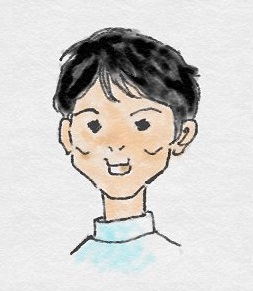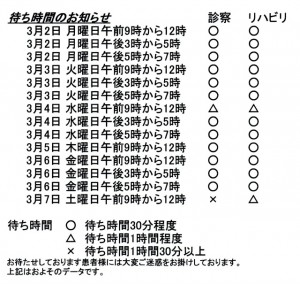リハビリ通信 No.146 頸椎の運動について
2015年03月15日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
頸椎は脊椎と呼ばれる背骨の首(頚部)の部分にあたる7つの骨の部分を言います。運動方向は大きく分けると①首がうなずく動作(屈曲)、後方に反らす動作(伸展)②首を横に振る動作・左右にまわす動作(回旋)③首をかしげる動作・横に反らす動作(側屈)に分かれます。 その中でも1番目の環椎と2番目の軸椎とで構成される環軸関節は主に回旋だけに関与しています。屈曲・伸展は環椎と後頭骨の関節、頸椎全体で作用しています。側屈は環軸関節以外の3番目から7番目の頸椎で主に作用しています。頸椎の高位、低位の位置により作用・働きは分別されています。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |


リハビリ通信 No.145 アキレス腱断裂について
2015年03月08日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
アキレス腱断裂の受傷好発年齢は、30~40代であり、若年層ではスポーツによる受傷が多く、高齢層では、日常生活の中で受傷することが多いと言われています。アキレス腱断裂の病態として、足関節に急激な伸張ストレスが加わったときに受傷しやすく、踵の骨から数cm上の部分で断裂することが多いです。 アキレス腱断裂の症状として、断裂部分に陥凹があり、触れると痛みを伴います。また、トンプソンテストが陽性となります。トンプソンテストとは、腹臥位(うつ伏せ)で膝関節を90°屈曲した状態で下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)を強くつまむと、正常では足関節が底屈するのに対して、断裂していると底屈しなくなります。 受傷後は、断裂部を縫合する手術療法を行うか保存療法を行うか選択をし、理学療法を行います。理学療法は、腱の修復過程を考慮しながら可動域や筋力の改善を図っています。 リハビリテーション科 服部 司 |


リハビリ通信 No.144 脊椎圧迫骨折について
2015年03月05日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
|
脊椎圧迫骨折とは、背骨の骨折です。上腕骨頸部骨折(上腕骨近位端骨折)・橈骨遠位端骨折・大腿骨頸部骨折(大腿骨近位端骨折)とともに「高齢者の4大骨折」のうちの一つであり、日常診療の中でもよくみかけられます。 本骨折は、骨粗鬆症により骨が弱くなり、尻もちをついたりして受傷することが多いですが、寝たきりの方で骨が著しく脆弱化している状態では起き上がっただけで骨折することもあります。 脊椎圧迫骨折は、読んで字のごとく、圧迫されることで骨が潰れるように骨折します。また、脊椎の前方が潰れるように骨折するのが特徴です。図のように骨の前方が潰れ、楔型の骨となってしまうため、本骨折を受傷された方は前屈み姿勢となっていまいます。 前屈みの姿勢では、良い姿勢で使う両脚の筋肉とは異なる筋肉を使うようになり、非常に偏った筋活動で歩行することになります。つまり、「使うところと使わないところ」が出てきます。そうすると、歩行時の筋肉による支持がアンバランスとなり、部分的に筋力低下が生じ、徐々に歩きにくくなる、転びやすいといったケースが散見されます。 我々理学療法士は、そのような患者様の筋力低下を見つけ出し、筋力トレーニングを行うことによって歩行時の不安定性改善、転倒予防に努めるようなアプローチをしています。 リハビリテーション科 小野正博 |