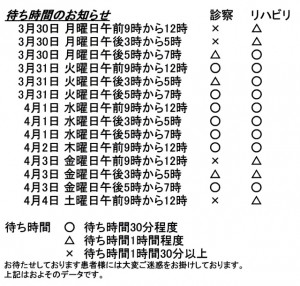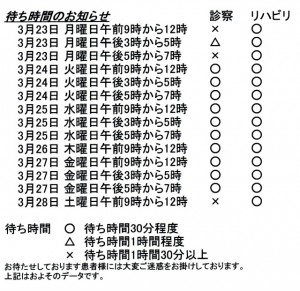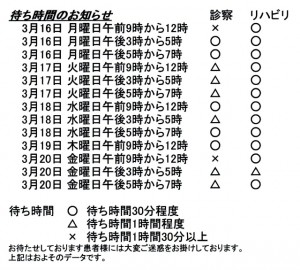リハビリ通信 No.148 Osgood-Schlatter病について
2015年04月01日(水) QAリハビリテーション科1新着情報
|
Osgood-Schlatter病(オスグッド・シュラッタ―)とは、運動負荷による大腿四頭筋の張力が繰り返し生じることによって、膝蓋腱の停止部である脛骨粗面部(上図の赤丸)に炎症や、部分的剥離が生じた疾患で成長期スポーツ障害の代表疾患の一つと言われています。好発年齢は、成長期である10代前半の男性に多く、症状として脛骨粗面部の圧痛と膨隆、運動時痛が認められます。 原因として、急激な骨の成長に対して筋肉の伸張が追い付かず、大腿四頭筋が短縮すること。また、部活動などで運動量が増加し、ジャンプやダッシュをすることで脛骨粗面部に負荷がかかり発症します。 理学療法では脛骨粗面部にかかる負荷を軽減するために大腿四頭筋の柔軟性の改善を図っています。 リハビリテーション科 服部 司 |

リハビリ通信 No.147 変形性膝関節症に対する運動について
2015年03月29日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
変形性膝関節症とは、膝関節の関節軟骨が摩耗した結果、痛みが生じてくるというものです。そしてテレビや雑誌などでも「変形性膝関節症に対する運動」として筋力トレーニングを推奨しているものをよく目にします。「筋肉を鍛える」と聞くと、運動しなければならないと考えるでしょうし、もちろんその通りなのですが、この運動の方法を間違えると更に関節軟骨を摩耗させることとなってしまいます。 日頃、患者さんからも「筋肉を鍛えるために頑張って歩いた方がいいですか?」とよく聞かれます。歩くということは、膝関節には荷重がかかります。そして、それが負荷となり、痛みを更に強くすることがあります。そのため理学療法の中では、「関節に荷重をかけることなく筋力を強化する」ということを実施しています。立位(立った状態)、歩行、階段昇降などでは、荷重がかかってしまいます。なので、寝た状態、座った状態など、膝関節に荷重が加わらない肢位で膝を伸ばす運動などを指導しています。その方が関節に負担をかけることなく、筋力を強化できると考えるからです。 我々理学療法士は、このような運動指導を行い、痛みを助長することなく筋力強化を図るような運動療法を実施しています。 リハビリテーション科 小野正博 |