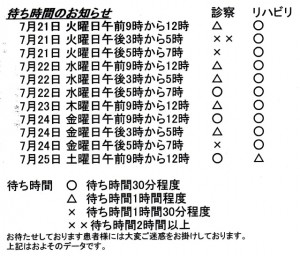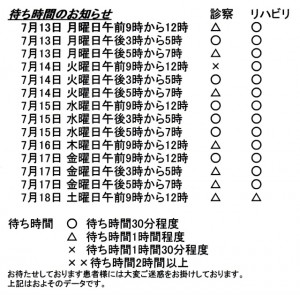リハビリ通信 No.163 膝蓋靱帯炎について
2015年07月26日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
膝蓋靱帯炎とは、膝蓋骨尖から脛骨粗面に付着する膝蓋靱帯が運動などにより炎症が起こる病態のことを言います。膝蓋靱帯炎は、スポーツ選手の中でも特にトップアスリートに多く発症すると報告されています。膝蓋靱帯に疼痛を認め、初期ではスポーツ後に疼痛が出現するが進行するとスポーツ中にも疼痛が出現すると言われています。 膝蓋靱帯の圧痛には、①膝関節屈曲位にて疼痛が出現する場合と②膝関節伸展位で疼痛が出現する場合、③膝蓋靱帯の膝蓋骨付着部に疼痛が出現する3パターンがあります。 ①膝関節屈曲にて疼痛が出現する場合、膝伸展機構への張力が増すことで、膝蓋靱帯表層への伸張ストレスが増大し、疼痛が出現すると言われています。 ②膝関節伸展位で疼痛が出現する場合、膝蓋靱帯の深層には膝蓋下脂肪体が存在し、膝蓋下脂肪体の滑走障害や炎症後の線維化が生じることで疼痛が出現すると言われています。 ③膝蓋靱帯の膝蓋骨付着部に疼痛が出現する場合、外側広筋や腸脛靱帯の過緊張による膝蓋骨の外上方への牽引力が増大すると膝蓋骨尖が突出し、膝蓋靱帯深層部に応力が集中し疼痛が出現すると言われています。 治療方法として、炎症の沈静化と軟部組織の柔軟性改善を図り、膝蓋靱帯にかかるストレスを軽減させることが重要になってきます。 リハビリテーション科 服部 司 |

夏期休業のお知らせ(再掲)
2015年07月25日(土) 新着情報
|
当クリニックでは下記の期間を夏期休業とさせていただきますので、ご案内いたします。休業期間は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、ご容赦くださいますように何卒よろしくお願い申し上げます。 夏期休業期間 2015年8月12日(水)~2015年8月16日(日) |


リハビリ通信 No.162 結帯動作について
2015年07月23日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
|
肩関節周囲炎の患者さんにおいて、手を後ろに回す動作である「結帯動作」が制限されていることをよく経験します。痛みで手を後ろに回せない方、痛みは無いけど硬くて回せない方など、症状は様々ですが、この結帯動作が制限されると日常生活動作が大きく制限されてしまうこととなるため、同制限を改善するために努めています。 この「結帯動作」は肩甲上腕関節(一般的に肩とされる部位)と肩甲骨の複合運動ですが、肩甲上腕関節レベルでの制限が大きく関与しているとされており、その中でも上方~後方の拘縮(固まって動かなくなること)が制限因子となります。この制限因子に対して筋収縮を促したり、筋を滑走させる操作を行ったり、ストレッチをしたりして関節の動きを獲得するような治療が必要となります。 各操作を行う上で痛みを伴うことがあるため、当院の理学療法士は痛みを出さない治療を心がけてアプローチしています。 リハビリテーション科 小野正博 |