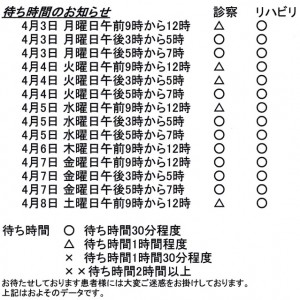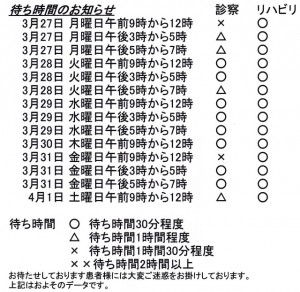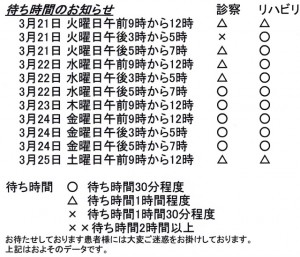骨粗鬆症とともに Vol.4 超音波骨密度測定装置(QUS法)
2017年03月26日(日) 新着情報1骨粗鬆症
|
骨粗鬆症の検査のひとつに骨密度検査があります。骨の構成要素であるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分の量(骨密度)を測定する検査です。骨密度検査もいくつかの種類がありますが、その中の一つである超音波(QUS)法は大きな設備を必要とせず、簡単で短時間ですむため、自治体の検診やイベントなどで多く使われています。 超音波法は骨に超音波をあてて、その伝わる速さや超音波の減衰の程度から骨量を測定する方法です。一般に音は硬いものほど早く伝わり、弱くなりにくいという性質があるため、その原理を用いて測定しています。おもにかかとの骨で測定することが多く、放射線を必要としないため、被爆がないこともメリットです。 しかしこの方法は感度が高くないため測定誤差が生じやすいことから、検診などのスクリーニングに用いられることが多く、骨粗鬆症診断基準(2012年改訂版)からは除外されているため診断には使用できません。 超音波法で骨密度検査を受けられた方で測定値が低い場合は、DXA(二重エネルギーX線吸収測定法)pQCT(末梢骨定量的CT法)MD(Micro densitometry法)などを行い、診断基準に当てはまるかどうかを評価する必要があります。 当クリニックではpQCT法を導入しております。検査台に前腕を乗せ、橈骨の骨密度を測定する方法です。低被爆であり15秒程度で測定可能です。お気軽に御相談下さい。 骨粗鬆症マネージャー 石山瑞穂
参考文献 骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン2015年版、骨粗鬆症治療の予防と治療ガイドライン作成委員会編集、ライフサイエンス社 2015 骨粗鬆症の最新治療、石橋英明監修、主婦の友社、2016 整形外科看護 第21巻8号(通巻266号)、メディカ出版、2016 |


リハビリ通信 No.230 片脚立位について
2017年03月24日(金) QAリハビリテーション科1新着情報
|
近年、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)が注目されるようになり、それを予防するための運動の一つに片脚立位があります。これは、バランスを取る上で重要な動作であり、歩行はこの片脚立位の繰り返しでもあるためにロコモティブシンドロームを予防する運動(ロコトレ)の一つとなっています。 片脚立位では支持脚と骨盤を結ぶ筋肉(主に中殿筋しっかり働くことで骨盤が水平化され、安定した片脚立位が可能となります。そのため、この中殿筋の筋力低下が生じると骨盤水平位を保つことができずにバランスを崩してしまうため、同筋の筋力トレーニングとして片脚立位が行われます。 そしてここで少し考えたいのが、トレーニングをする際の姿勢です。片脚立位を行う際、骨盤の肢位によって作用する筋肉が変化します。骨盤前傾位では中殿筋の後方の線維が作用し、骨盤後傾位では中殿筋の前方線維や大腿筋膜張筋といった筋肉が作用します。そのため、骨盤の肢位によって作用する筋肉が変化するため、我々理学療法士は、姿勢を変化させながらの片脚立位にて筋力低下を起こしている筋肉を見つけ、選択的に筋力トレーニングを行うといった運動療法を行っています。 リハビリテーション科 小野正博 |