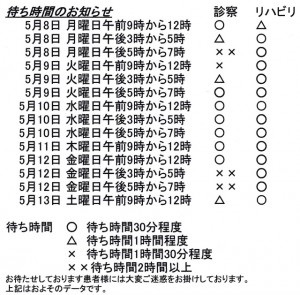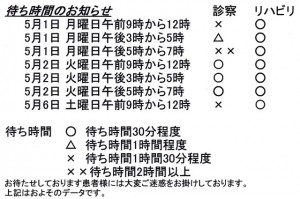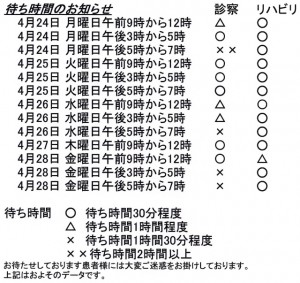リハビリ通信 No.233 膝関節伸展運動について
2017年05月19日(金) QAリハビリテーション科1新着情報
|
骨盤後傾位 骨盤前傾位 膝関節周囲の筋力強化を図るために「膝関節伸展運動」はよく用いられる方法ですが、運動をする際の姿勢によって作用する筋が変化します。 膝関節伸展の作用を持つ筋として代表的なものに大腿四頭筋があります。読んで字のごとく、4本の筋肉が1つにまとまった形となっている筋肉です。この筋肉は大腿直筋、内側広筋、中間広筋、外側広筋の4つで構成されており、その中でも大腿直筋は他の筋肉に比べて大きい(2関節筋)のが特徴です。人間の身体において大きい筋肉は発揮できる筋力も大きく、使いやすい筋肉であることが言えます。つまり、膝関節伸展運動で大腿直筋が優位に作用した場合、内・外側広筋、中間広筋といった筋(単関節筋)は拘縮(固まってしまうこと)や筋萎縮(筋肉が痩せてしまうこと)が生じ、筋力低下や可動域制限の原因となってしまいます。そこで、座位にて膝関節伸展運動を行う際、骨盤前傾位での運動と骨盤後傾位での運動に分けて行い、どちらの筋肉を優位に作用させるかをコントロールしながら膝関節伸展運動を行うことが重要です。 骨盤後傾位での膝関節伸展運動では、大腿直筋が優位に作用してしまう運動となります。骨盤前傾位での膝関節伸展運動では、内・外側広筋、中間広筋といった単関節筋が優位に作用する運動となります。 当院の理学療法では、どの筋肉を強化するのか、どの筋を優位に作用させるのかを考え、姿勢や運動を選択しながらアプローチしています。 リハビリテーション科 小野正博 |



リハビリ通信 No.232 飲酒と骨折について
2017年04月30日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
お酒が弱い女性は年齢を重ねると骨が折れやすくなることが慶応大などの研究チームの調査で分かりました。女性は閉経後に骨粗鬆症になりやすいがアルコールの分解に関わる遺伝子の働きが弱いと更に脆くなる可能性があると言われています。アルコールを分解する時に働く酵素を作る遺伝子「ALDH2」の働きが生まれつき弱い人はアセトアルデヒドをうまく分解できず、酒酔いの原因となります。つまりアセトアルデヒドが上手に分解できないという事は、お酒に弱いと言えます。 中高年の女性で大腿骨骨折を発症した人は、骨折しない人に比べ「ALDH2」遺伝子の働きが弱かった事が分かってきました。骨折リスクは約2.3倍高く、動物実験では骨を作る骨芽細胞にアセトアルデヒドを加えると働きが弱まり、ビタミンE(ピーナッツ類・アボガド・うなぎ・西洋かぼちゃ)を補うと機能が回復しました。 お酒に弱い人が過剰な飲酒をするとアセトアルデヒドがうまく分解できずに、骨を作る骨芽細胞が抑制され骨が脆くなる可能性があります。予防としてはビタミンEの適度な摂取とアルコールの抑制で予防できる可能性があります。 リハビリテーション室長 見田忠幸
|