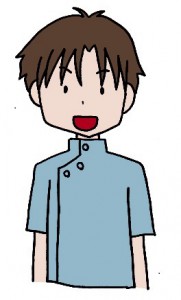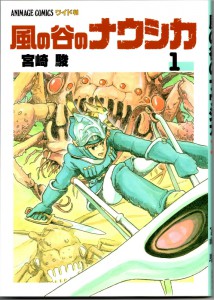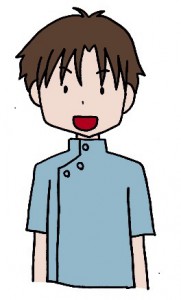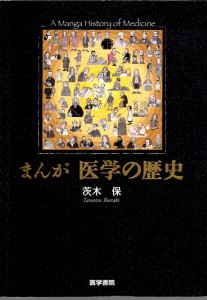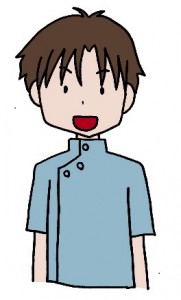リハビリ通信 No.32 変形性膝関節症の骨・軟骨の問題
2012年07月12日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
|
変形性膝関節症の患者さんの中には、「変形した骨が痛い」「擦り減った軟骨が痛い」と訴える方が多くいらっしゃいます。しかし、実際には、骨は骨折以外ではほとんど痛みが出ませんし、軟骨そのものには感覚神経がないため擦り減っても痛みを感じることは考えにくいです(半月板の血行の多い部分では痛みを感じます)。 骨や軟骨の痛みとして訴えられているものの多くは、軟骨や半月板が傷むことで関節が本来の動きから逸脱して動くことで、関節を包んでいる関節包の内側を覆う滑膜に炎症が起こることなどが原因と考えられます。 リハビリテーション科 奥山智啓
|

風の谷のナウシカ 漫画版全7巻
2012年07月07日(土) 新着情報
|
映画「風の谷のナウシカ」は、とてもよく知られたアニメ映画ですが、漫画版の「風の谷のナウシカ」はラストが大きく異なります。漫画版は全7巻ですが、アニメ版は漫画版の2巻くらいまでのストーリーの様です。 漫画版ではアニメ版よりも更にストーリーが広大なスケールで展開していき、最後は驚愕のクライマックスになります。大変おもしろいですよ。 それにしてもストーリーは難解ですね。ちょっと読んだだけでは、なかなか理解できません。読むのに随分時間がかかります。 診察の待ち時間が長いときには、最適ですね。皆様、是非ご覧下さい。 クリニックの本棚に置いています。
|

リハビリ通信 No.31 肩関節の骨形状について
2012年07月06日(金) QAリハビリテーション科1新着情報
|
骨の形状と構成には意味があります。 盛り上がっている部位は筋の付着部になっており、腱が滑走する部位では溝になり、関節内で骨が擦れ合う部位ではスケートリンクより滑りやすくつるつるとして、状況と環境により骨の形状は変化していると考えられます。 例えば肩関節の上腕骨で言えば小結節と大結節があり、両方ともに突出し、前方にある小結節は内旋筋が付着し後方にある大結節は外転・外旋筋が付着しています。そして、肩甲骨上部には棘上筋が入るだけの受け皿つまり空間があり、上肢を挙上する際、肩峰・鳥口肩峰靭帯・鳥口突起で作られるアーチが棘上筋の働きを助けています。 アーチの機能が十分に発揮できない場合、インピンジメント(大結節と肩峰・鳥口肩峰靭帯が衝突する)が起こり、上肢が挙上できない場合があります。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

まんが 医学の歴史
2012年06月28日(木) 新着情報
|
「まんが医学の歴史」の著者、茨木保先生は現在神奈川県で「いばらぎレディースクリニック」を開業しておられます。 茨木先生は奈良医大出身で私の2年先輩に当たります。面識はございませんが、すごい才能に溢れた先輩ですね。医師と漫画家の二足のわらじを履いておられます。「Dr.コトー診療所」の監修者としても有名です。 皆様一度ご覧下さい。クリニックの本棚に置いています。 |

リハビリ通信 No.30 こむら返りの痛み
2012年06月27日(水) QAリハビリテーション科1QA整形外科1新着情報
|
久しぶりに運動した時や夜中に寝ている時などにふくらはぎがつる経験をされたことのある方は多いと思います。こむら返りは「腓腹筋痙攣(ひふくきんけいれん)」と呼ばれ、ふくらはぎの筋肉が異常な緊張を起こして弛緩しない状態になり、痛みを伴う症状です。 私たちが運動を行うときは、筋肉の収縮と弛緩を調節することで、バランスのとれた動きが可能となります。この調節は、脳や脊髄などの中枢から信号が神経を伝って筋肉に送られ、筋肉が収縮し、次に筋肉や腱のセンサーから信号が中枢に送られ、どれくらい収縮するか弛緩するかが決められています。この仕組みが何らかのトラブルを起こすとこむら返りが生じるといわれています。 筋肉の異常収縮が起こりやすくなる状態は、大きく分けて2つ考えられます。ひとつは運動などで多量の汗をかいた時や、水分を大量に摂りすぎた時に、血液中の電解質(ナトリウムやカリウムなど)のバランスが崩れ、神経や筋肉が興奮しやすくなっているときです。もうひとつは、久しぶりに運動した時、長時間の立ち仕事をした後、寝ている時に足の温度が低下した時などに筋肉や腱のセンサーの感度が鈍くなっている時です。筋肉の緊張状態が続くと、血行が悪くなり、筋肉を弛緩させる調節がうまくいかず、こむら返りが起こりやすくなります。 ただし、ほとんどのものが疾患とは無関係に起こるものなので、予防が大切となります。こむら返りがひどい時には、薬などが用いられますが、運動前後や立ち仕事の後では、筋肉の疲労を取り血行を良くする意味から、軽い足首の運動やストレッング、運動中はスポーツドリンクなどで水分と電解質の補給を心がけると良いと思います。 リハビリテーション科 奥山智啓 |