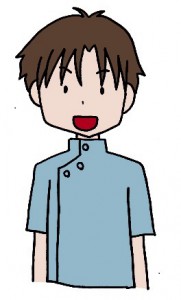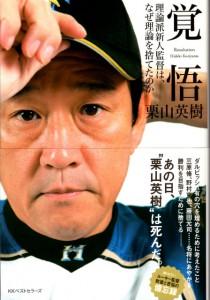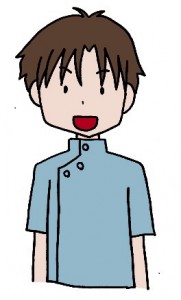リハビリ通信 No.53 肩関節の複合運動について
2012年12月29日(土) QAリハビリテーション科1新着情報
|
肩関節の運動動作は複合的な運動の組み合わせにより成り立っています。 日常生活の実際の動作では上肢を挙上・降ろす動作(屈曲・伸展)と外側から挙上・降ろす動作(外転・内転)と内側・外側に回す動作(内旋・外旋)が協調し合い一つの動作として成り立っています。 例えば手のひらを内側に向け腕を伸ばし挙上、そして、外に手を拡げながら意識して手のひらは上向きに降ろす時(内転動作)、最後は「気をつけ」の変則的な姿勢(手のひらは外に向け母指は後方つまり最大外旋位)になります。しかし、挙上から外に手を拡げながら無意識に手を降ろすと内側に自然と手のひらを回しながら(自動回旋)上肢を降ろし最初の「気をつけ」の姿勢になります。つまり、無意識に効率よく複雑な運動を実施しています。 肩関節は自由度の高い関節であるのと同時に、日常生活の場面では効率よく必要な動作だけが出来るように柔軟に対応しています。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

年末年始休業のお知らせ(再掲)
2012年12月25日(火) 新着情報
|
当クリニックでは下記の期間、年末年始休業とさせて頂きますのでご案内いたします。休業期間中は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、ご容赦くださいますように何卒よろしくお願い申し上げます。 年末年始休業期間 2012年12月30日(日)~2013年1月4日(金) |

リハビリ通信 No.52 関節が硬くなる要因 -皮膚-
2012年12月24日(月) QAリハビリテーション科1新着情報
|
関節が硬くなる重要な要因に、皮膚・筋・靭帯・関節包などの軟部組織の問題があります。今回はその中でも皮膚による問題について紹介させていただきます。 皮膚は関節の運動に伴って伸張したり滑走したりして、部位によっては動きに応じて大きく形を変えています。例えば、肘の裏側の皮膚をつまんで肘関節を屈曲すると、関節は曲がりにくくなります。これは、肘関節を曲げるときに本来伸びなくてはならない皮膚が伸びないために生じる現象です。このように、皮膚の動くゆとりが無くなると、関節の動きに影響を及ぼします。 臨床においては、外傷や手術により皮膚が損傷を受けた場合に、損傷を受けた皮膚は修復とともに周囲の軟部組織と癒着したり瘢痕組織を形成したりします。それにより、皮膚に伸びたり滑ったりするゆとりが無くなり、関節の可動域が制限される要因の一つとなる可能性があります。 そのため、外傷や手術により皮膚に大きな損傷を生じた場合は、癒着や過度な瘢痕形成を予防するため、適切な時期に皮膚の伸びや滑りを維持することが重要となります。ただし、皮膚は身体の中で最も受容器が多い組織であり、損傷後に早期から強い刺激を入れ過ぎると、疼痛を引き起こしたり、ケロイドを形成したりする可能性があるため、適切な刺激が加わるように配慮が必要となります。 リハビリテーション科 奥山智啓 |

「覚悟 理論派新人監督は、なぜ理論を捨てたのか」
2012年12月22日(土) 新着情報
|
栗山英樹監督の「覚悟 理論派新人監督は、なぜ理論を捨てたのか」を読みました。 日本ハムファイターズの監督として1年目からリーグ優勝を成し遂げた栗山英樹監督ですが、確か下馬評は低かったですね。日本ハムファイターズからは絶対的エースのダルビッシュ有が抜けて、ドラフト1位の投手にも入団を拒否されて、何より栗山英樹監督に現場の実績が全くないことが評価を随分低くしていたようです。それがふたを開けてみれば見事に接戦を制してのリーグ優勝、それに至るまでの一人一人の選手とのやりとりや心の交流が本書では生き生きと伝わってきます。 理論派の新人監督が‘理論を捨てた’、とタイトルでは言っていますが、本文では「理論を持った上で、それに固執しないこと、肌感覚を敏感にさせることこそが、勝利のために必要だったのだ。」と栗山英樹監督は述べておられます。 栗山英樹監督は初めて監督を経験して一番の衝撃は、プロ野球という存在そのものが衝撃だったと述べておられます。毎日が苦しい、一日中苦しいと…。そして毎日自分にこう言い聞かせているそうです。「明日はいいが、今日だけは全力を尽くせ!」 栗山英樹監督は現役最後の年に、新しい監督としてスワローズにやってきた野村克也監督に「覚悟に優る決断なし」と教わったそうです。そして野村克也監督は、覚悟するこということは、結果を全て受け止める心構えで、迷いなく勝負に挑むということ、それを持って前へ突き進めと選手達に説いたそうです。栗山英樹監督は少しでも自分のためを考えたら、それは覚悟ができていないということだと述べておられます。 最後まで感謝の言葉で締めくくっておられる栗山英樹監督が、理論と情熱と人心掌握術によって、経験に優る強敵に競り勝ったということも納得できるように思えました。 皆様、是非お読み下さい。 |

リハビリ通信 No.51 肩甲骨の動きについて
2012年12月15日(土) QAリハビリテーション科1新着情報
|
肩甲骨は上肢の動きとともに上方回旋し肩甲骨は3軸性の運動があります。①上・下方回旋 ②前・後傾 ③内・外転です。 上肢を挙上する場合、上肢が挙がるにつれ肩甲骨も上方回旋・後傾・内転をします。肩甲骨の動きが挙上する際には重要な役割を担っています。 従って、肩甲骨の正常な動きが出ないと上肢は挙上することができません。例えば肩関節周囲炎、腱板断裂、胸郭出口症候群などの疾患は、各々の病態の理解とともに肩関節の癒着・拘縮を取り除き、肩甲骨自体の動きの評価と肩甲骨周囲筋の協調性向上を行います。 肩甲上腕関節と肩甲骨の相互を考慮し治療を進めることが必要です。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |