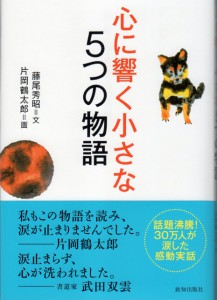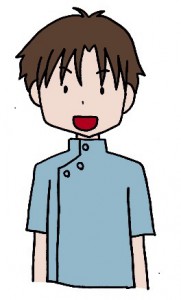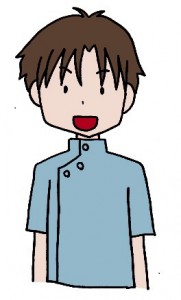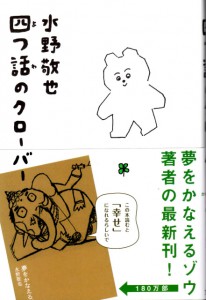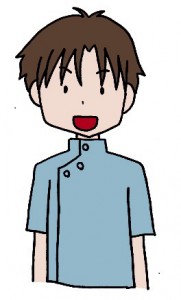「心に響く小さな5つの物語」
2013年02月11日(月) 新着情報
|
「心に響く小さな5つの物語」を読みました。 時間は音符に例えられるそうです。並んでいる音符は同じでも指揮者によって奏でる音楽は異なってくるように、時間もそれを使う人によって大きく違ってきます。 本書では与えられた時間、場所、環境をそれぞれの使い方で使い、素晴らしい音楽を奏でた人たちのお話を紹介しています。 大変短いエピソード集ですが、心を打つ話ばかりです。 片岡鶴太郎さんの絵も素敵です。 皆様、是非ご覧下さい。 |

リハビリ通信 No.58 関節が硬くなる原因 -関節包-
2013年02月09日(土) QAリハビリテーション科1新着情報
|
関節包は関節の連結する部分の全体を覆う線維性の膜であり、関節の可動性や安定性に関与しています。 関節包は部位によってはハンモックに例えられ、関節の運動に伴って拡がる組織です。この関節包が拡がるパターンは各関節によって異なり、関節包の中で各関節は綺麗な運動軌跡を保ちながら動いています。 しかし、関節の運動に伴って関節包が大きく拡がる部分のゆとりが無くなると、骨の動きは偏位し、関節は綺麗な運動軌跡を描くことができません。それにより、関節の可動域制限や痛みが生じる原因の一つとなります。 そのため、関節が綺麗に動くためには関節包のゆとりを維持することが大切になります。一度硬くなってしまった関節包を拡げていくには、関節包を適度に伸ばしていく必要があります。関節包はムリに伸ばすと痛みや関節の不安定性を伴うため、弱い力での伸張を繰り返しながら、持続的に伸ばしていきます。また、関節包は深部にあり、筋肉や靭帯など周囲の組織と連結しているため、周囲の組織も含めた全体的な柔軟性が必要となります。 リハビリテーション科 奥山智啓 |

リハビリ通信 No.57 投球肩障害について
2013年02月04日(月) QAスポーツ整形1QAリハビリテーション科1新着情報
|
投球肩障害は大きく分けると肩関節の前方部分(棘上筋・肩甲上腕靭帯)、上方部分(関節唇)、後方部分(棘下筋)に対しストレスが加わることにより投球動作時に損傷と疼痛が発症すると考えられます。要因として、①投球フォーム②股関節・下肢の硬さ③筋のバランス(肩関節インナー・アウターマッスル、肩甲骨固定筋、体幹・下肢のバランス)が考えられます。 投球肩障害の中でも関節唇損傷は上腕二頭筋長頭腱の付着部がストレスにより、剝がれてくるもので、SLAP損傷と呼ばれ、損傷度合いによりタイプが分類されています。場合により手術も行われます。 理学療法では病態に至る経緯を評価し、癒着・拘縮を除去するのと同時に筋の協調性を高め、投球フォームの指導を行います。また、手術をしているのか、保存療法か、スポーツ復帰の時期を考慮しながら理学療法を実施します。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

「四つ話のクローバー」
2013年01月27日(日) 新着情報
|
「夢をかなえるゾウ」の著者、水野敬也氏の「四つ話のクローバー」を読みました。 見つけた人には幸福が訪れるという「四つ葉のクローバー」に引っかけた「四つ話」には幸福を呼び込むための具体的なヒントが詰まっているかもしれません。 私はちょっと切ない「氷の親子」が最も気に入りました。 皆様、是非ご覧下さい。 |

リハビリ通信 No.56 関節が硬くなる要因 -靭帯-
2013年01月24日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
|
靭帯は強靭な結合組織の集まりで構成され、骨と骨を繋ぎ関節を形づくります。靭帯には若干の弾性がありますが、筋肉のような伸縮性はなく、長さや形態の変化が少ないヒモのような組織です。しかし、靭帯においても周囲の組織と癒着したり、組織の拡がりが低下したりした場合には、関節の可動域を制限します。 靱帯の役割は、関節において骨と骨が離れてしまわないように位置関係を保持し、関節の運動軌跡がスムースになるように誘導をすることです。また、靭帯は関節の運動が異常な方向へと逸脱しないように動きを制動する役割も果たしています。そのため、関節に正常とは逸脱した無理な力が加わると、靱帯は引っ張られ、許容範囲を越えると部分断裂や重度の場合は完全断裂をしてしまいます。 外傷による靭帯損傷などで関節を長期間固定した場合や、長期の不動状態が続いた場合には、靭帯が癒着などを引き起こし、関節の可動域を制限する可能性が生じます。 靭帯の問題によって関節の動きが低下した際には、関節の可動域訓練を行うことが重要となります。ただし、靭帯損傷後においては、損傷靭帯の修復が十分でない時期に負荷を加え過ぎたり、正常とは逸脱した関節運動を行ったりすると、靭帯が緩くなり関節が不安定になる可能性があります。そのため、理学療法では靭帯への負荷を加える時期と負荷量、関節の運動方向に注意をしながら、関節の安定性と可動性の双方の獲得を目指していきます。 リハビリテーション科 奥山智啓 |