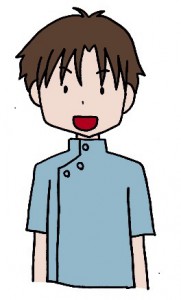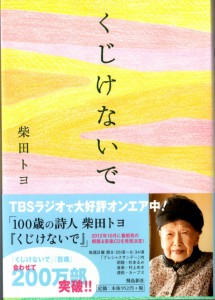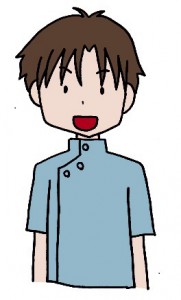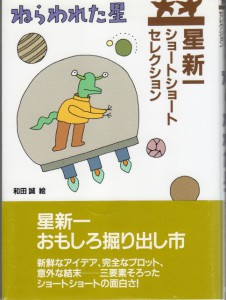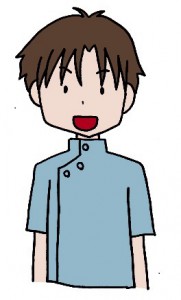リハビリ通信 No.61 筋膜について
2013年03月02日(土) QAリハビリテーション科1新着情報
|
筋膜は簡単に言うと筋を覆う膜です。 働きとしては①筋を区分けしている②筋の引っ張る力に対する強さを持っている③筋の張力を腱に伝える働きを持っている④筋の滑走性を高めるなどがあります。 実際の臨床では筋の打撲・骨折など炎症が起きると、筋膜と言う容器があることにより筋の内圧を一層、高め疼痛が出現し、関節が動かしにくい状態になります。また、発症経過後、筋と筋膜に癒着が起きると拘縮の一要因になります。 人間の体は筋肉と骨の働きだけで、スポーツ・日常生活の動作を行うのではなく、その他の軟部組織も関与して動作を遂行しています。治療は様々な軟部組織の影響を考慮しながら進める必要があります。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

「くじけないで」
2013年02月23日(土) 新着情報
|
柴田トヨさんの「くじけないで」を読みました。 柴田トヨさんは92歳から息子さんの勧めで詩を書き始め、「くじけないで」は産経新聞の「朝の詩」という詩の投稿欄の常連であった柴田トヨさんが98歳の時に刊行されたミリオンセラーの詩集です。 柴田トヨさんは「私の軌跡」でこの様に言っておられます。 どんなにひとりぼっちでさびしくても考えるようにしています。「人生、いつだってこれから。だれにも朝はかならずやってくる」って。 誰しも励まされる言葉ですね。 先日、柴田トヨさんがお亡くなりになったのは本当に残念に思います。 ご冥福をお祈りいたします。 |

リハビリ通信 No.60 関節可動域訓練について
2013年02月21日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
|
関節が動く範囲を維持または拡大する訓練を関節可動域訓練といいます。 例えば、膝を曲げる方向に可動域を拡大したい場合、膝を無理やり曲げたり、痛みを我慢して押し込んだりしても、膝は綺麗に曲がるようになるわけではありません。 関節にはそれぞれその人が本来持っている運動軌跡があります。痛みが生じているということは、その人が本来持っている運動軌跡から逸脱していたり、組織に何らかの負担がかかり炎症を起こしている可能性が考えられます。そのため、無理な関節運動は痛みや筋の緊張を助長して、余計に関節の可動域を制限してしまうことがあります。また、硬い組織と柔らかい組織のバランスが悪い状態で無理に組織を伸ばそうとすると、柔らかい組織ばかりが伸びてしまい、関節が不安定な状態になる可能性があります。そのため、無理なストレッチングには注意が必要です。 関節の運動軌跡は、関節の形態や軟部組織の状態、普段の動作での使い方などが影響して、その人なりの軌跡ができあがっていきます。つまり、片側に外傷や障害、変形がある場合には、良い側の関節の動きが一番のお手本になります。また、両側に何らかの問題がある場合でも、基本的には痛みが出ないこと、関節が硬い状態で無理に動かさないことが綺麗な運動軌跡を引き出していくために重要となります。 関節可動域訓練では、軟部組織の硬いところや短くなっているところ、周りの組織と引っ付いているところなどを改善し、組織の柔軟性のバランスを整えることが重要となります。また、痛みや安静固定などにより関節が不動の状態となるような場合では、関節の拘縮ができる限り起こらないように予防を行うことが重要です。そして、関節の周りにある軟部組織が柔らかくなった分、痛みのない範囲で可動域を拡げていくことで、その人なりの正常な運動軌跡を引き出すことを目指していきます。 リハビリテーション科 奥山智啓 |

「ねらわれた星」
2013年02月16日(土) 新着情報
|
星新一ショートショートセレクション「ねらわれた星」を読みました。 私(院長)が最も印象に残っているのは、「おーい、でてこーい」です。私が小学生か中学生かの時にも読んだと思うのですが、ストーリーは当時から鮮明に憶えています。 本作品は昭和46年頃の作品だそうです。 現在の環境問題、原発の問題まで予見しているかのようですね。 星新一、おそるべし! 皆様、是非ご覧下さい。 |

リハビリ通信 No.59 肩こりの筋、僧帽筋について
2013年02月14日(木) QAリハビリテーション科1新着情報
|
僧帽筋は〝 肩こり 〟と深い関係があります。 肩こりは僧帽筋の上部線維が過緊張によりスパズム(れん縮)・循環障害になっている状態です。僧帽筋は外後頭隆起(頭蓋骨の底部)、項靱帯(首の後部)から肩甲骨を包み込むように付着しており、治療としては頚部(首の部分)、肩関節の周囲筋も含めて考える必要があります。 そもそも、疼痛が出現するのは、炎症、筋の緊張などが要因で痛み発痛物質が、その場所に留まる事により痛みとして感じます。従って、痛み発痛物質を血流循環により除去することが重要です。ストレッチ・軽い運動により筋の収縮を促し血流循環を良くすることが改善に繋がると考えられます。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |