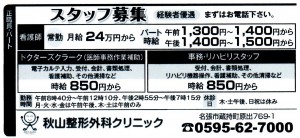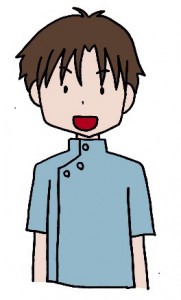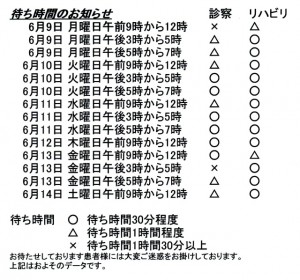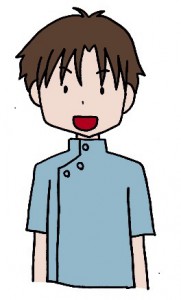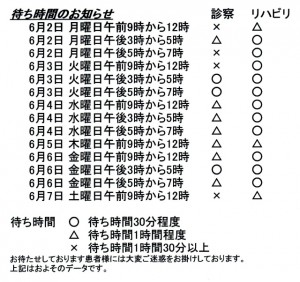リハビリ通信 No.117 肩関節の可動域制限と機能解剖について
2014年06月15日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
上肢の挙上は上腕と肩関節の動き(肩甲上腕関節)と肩甲骨の動き(肩甲胸郭関節)が一緒になり、上肢の挙上という一連の動きが行われます。肩関節疾患の患者さんの場合、とくに肩関節周囲炎では最初に理学療法を実施するときに2点について患者さんに質問しながら、評価を行います。 ①夜間に痛くて目を覚ましますか?or夜に何度も目を覚ますか、寝ることができませんか? ②自分の手を90°以上あげる事ができますか? この2点が共にある人は治療が長期に及ぶ可能性があります。(週2~3回の通院で4ヶ月以上) これには理由があり、2つの質問から癒着の場所と範囲が、おおよそ特定することができます。もちろん可動域・触診を行い最終的には原因を絞り治療を行います。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |


リハビリ通信 No.116 膝半月板の血行について
2014年06月08日(日) QAリハビリテーション科1新着情報
|
半月板の血行について、以前は血行がなく、一度断裂すると自然治癒しないと言われていました。しかし、研究により、半月板実質部外縁1/3から中1/3にかけて血管が存在し、関節包由来の血管より栄養を受けています。内側の1/3には、血管が存在しておらず滑液より栄養を受けていることがわかってきました。この研究が現在の半月板部分切除術か縫合術かを選択する基礎となってきています。 半月板実質部外縁1/3には血行が豊富でこの部分をred-red zoneと呼び、中1/3をred-white zone、内側1/3をwhite-white zoneと呼ひます。一般的に血行のある部分は、半月板縫合術の適応で、血行の乏しい部分は、半月板部分切除術を施行されていました。 しかし、近年の研究より半月板を温存することによるメリットを最大限に活かせるようにいろいろと検討されるようになり、半月板縫合術の適応を血行の豊富な部分から乏しい部分へと拡大しつつあります。 リハビリテーション科 服部 司 |